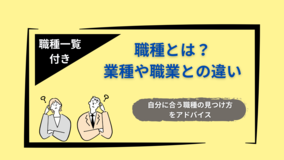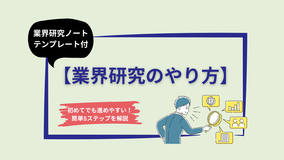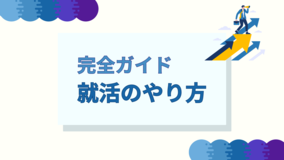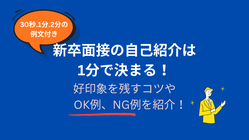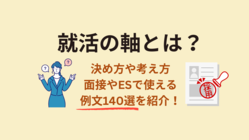業界や企業研究を進めていく中で、「当社はBtoB事業を展開しております」といった説明を見聞きすることがあるかと思います。
しかし、「BtoBって何だろう?」「分かりやすく説明して欲しい」と思われる学生の方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では「BtoB」「BtoC」を詳しく解説するとともに、「CtoC」「BtoG」「DtoC」「BtoE」「GtoC」といったビジネスモデルについてもご紹介。それぞれの違いを理解し、就職活動に役立てていただけたら幸いです。
目次
本記事の監修者

doda新卒エージェント統括部
米田 圭佑さん
前職の経験からIT領域での支援を得意とし、就職した後に身につくスキルやエンジニアとしての働き方を具体的にアドバイスすることができます。特にひとりではなかなかイメージしづらい各企業の事業内容などを、皆さんが理解し働くイメージができるようお手伝いします。
学生個人の価値観を深く理解したうえで、本人が自発的にキャリアを選択していけるようなサポートを心がけています。
BtoBとは?簡単に解説

まず、「BtoBの定義」「代表的なビジネスモデル」などから解説します。併せて、BtoBと呼ばれるものには、どのような業界や企業があるのか具体的に見ていきましょう。
BtoBの定義(Business to Business)
BtoBは「Business to Business」の略で、企業間取引そのものを意味します。例えば、「部品メーカーが自動車メーカーへ部品を納める」、「IT企業が企業向けのシステムを提供する」といった取引は、まさにBtoBの典型的な例です。
BtoBビジネスの基本的な仕組み
BtoBビジネスは、「ヒアリング→見積提案→契約→販売や導入→請求」といった流れで進められるのが一般的です。BtoCのように「店頭で購入」という即決型のビジネスモデルではなく、企業間で時間をかけて取引が成立するのが特徴です。
また、BtoBにおける取引では「一度契約を結んで終わり」ではなく、システムの保守やアフターサポート、継続提案など継続的に取引が続きます。ビジネス取引に関わる部署や職種も多く、営業やカスタマーサポートなど、多くの部門が連携して取引を支えているのも、BtoBビジネスならではの特徴といえるでしょう。
5分で完成!AIがあなたの強みを分析し、自己PRを自動作成する無料サービスをご存知ですか?「色々考えているけど、自己紹介のネタが見つからない」と悩んでいる方は、dodaキャンパスの自己分析サポートを活用して、新たな視野を採り入れましょう!
\自己分析から始めたい方へ/
BtoBの代表的な業界・企業例(メーカー・IT・商社など)
BtoBビジネスは、特定の業界や企業だけでなく、さまざまな分野で展開されています。具体的に、どのような業界や企業でBtoBのビジネスモデルが展開されているのか、詳しく見ていきましょう。
【BtoBビジネスの代表的な例】
| 業界 | 代表的な事業やビジネスモデル | 企業例 |
|---|---|---|
| メーカー | 電子部品の供給、産業機械・プラントの設計・製造 | キーエンス、村田製作所、三菱重工業 など |
| IT | 基幹システム開発、業務クラウド(グループウェア・CRM等)の提供や運用 | NTTデータ、富士通、サイボウズ など |
| 商社 | 原材料や部品の調達、海外取引の仲介、事業投資・サプライチェーン構築 | 三菱商事、伊藤忠商事、住友商事 など |
| 建設 | マンションや戸建ての建築、オフィスビルや工場建設、社会インフラ構築 | 清水建設、鹿島建設、大林組 など |
どの業界にも共通しているのは、「企業の事業を裏側から支えている」という点です。BtoBの仕事は目立たないことも多いですが、その仕組みがあるからこそ、社会や産業が成り立っています。
BtoBやBtoCなどのビジネスモデルを理解すると、「自分はどんな相手に価値を届けたいか」という就活の軸が見えてきます。企業を選ぶときは、業界の知名度よりも「自分が活躍できるフィールド」を知ることが大切。dodaキャンパスの「就活軸診断」を通じて、あなたに合う企業や働き方につながるヒントを見つけてみませんか? 診断結果は、そのままキャリアノートに反映できます。
\自分の就活の軸を明確にしたい方へ/
BtoBとBtoCの違い

就活で業界や企業を選ぶ際には、BtoBとBtoCなど、それぞれのビジネスモデルの違いを理解しておくことはとても重要です。なぜなら、事業取引の相手が企業か個人かで仕事の進め方や、生かせる強みが違うからです。
取引相手や営業スタイル・事業規模の3つの視点から、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
取引相手や販売先の違い
BtoBとBtoCの違いを理解するうえで、もっとも基本となるのが「取引相手」です。誰に商品やサービスを届けるのかによって、ビジネスの進め方や求められるスキルが変わります。
| 項目 | BtoB(企業間取引) | BtoC(個人向け取引) |
|---|---|---|
| 取引相手 | 企業、法人 | 個人消費者 |
| 具体的な交渉先 | 経営層、購買担当者、技術者 など | 一般ユーザー |
BtoBの取引では「相手の課題を理解して信頼を築く力」、BtoC取引では「消費者の心をつかむ発想とスピード」が求められます。自分がどんな場面で力を発揮できそうかを意識すると、業界選びもやりやすくなるでしょう。
営業やマーケティングの進め方の違い
BtoBとBtoCでは、営業手段やマーケティング手法も違います。どのように相手へ価値を伝えるか、それぞれの違いを比較してみましょう。
| 項目 | BtoB(企業間取引) | BtoC(個人向け取引) |
|---|---|---|
| 営業スタイル | 顧客の課題を聞き出し、最適な解決策を提案する「課題解決型営業」が多い | より多くの個人に商品を知ってもらい、購入につなげる「商品提案型営業」 |
| マーケティング手法 | 展示会やセミナー、ウェビナーなどでリード(※1)を獲得し、ナーチャリング(※2)を行う | Webサイト、SNS、テレビCM、店頭販売などで認知を拡大 |
※1 リードとは:自社の商品・サービスに関心を示した見込み顧客のこと
※2 ナーチャリングとは:リード(見込み顧客)に継続的に情報提供し、購買意欲を高めてもらうよう関係強化すること
BtoBの営業は、顧客企業の課題を丁寧に分析し、最適な解決策を提案して信頼を積み上げていくスタイル。一方、BtoCはより多くの人に興味を持ってもらうアプローチ。商品企画では創造性・企画力、エンドユーザー対応ではコミュニケーション能力が求められます。
取引の流れや金額、事業規模の違い
BtoBとBtoCでは、1件あたりの取引規模や期間、ビジネスの進め方が大きく異なります。
| 項目 | BtoB(企業間取引) | BtoC(個人向け取引) |
|---|---|---|
| 取引の流れ | 課題ヒアリング→見積・提案→契約→販売・導入→請求→アフターサービス ※取引サイクルが長い |
店頭やWebサイトでの販売→購入 ※購入サイクルが短い |
| 取引金額 | 1件あたりが大きい。事業によっては数億円以上になることも | 1件あたりは少額(数百円~数十万円程度が多い) |
| 事業規模 | 1件あたりの規模が大きく、産業そのものを支えるケースも多い(例:自動車部品の納入 など) | 1件は小規模だが顧客数が多く市場は広い(例:コンビニで商品を販売 など) |
BtoBは、ひとつの取引が業界全体の仕組みに影響を与えることがあります。一方のBtoCは、より多くの人の暮らしに直結する取引が多く、景気や一般消費者の動向が企業実績にダイレクトに影響する傾向があります。
BtoB・BtoCなどビジネスモデルの特徴を理解したら、次は「自分の強み」を見つけるステップへ進みましょう。5分で完成!AIがあなたの強みを分析し、自己PRを自動作成する無料サービスをご存知ですか?dodaキャンパスの自己分析サポートを活用して、新たな視野を採り入れましょう!
\まずは自己分析から/
BtoB企業で働くメリット

BtoBで働くメリットとしては、大きくわけて「安定性がある」「社会の根幹を支えられる」「長期的なキャリア形成ができる」という3つのポイントがあります。
企業同士の長期的な取引を軸にしているため、景気の波に影響されることも少なく、社会や産業を支えるため大きなやりがいを得ることも可能です。
安定した業績と個人消費の動向に左右されにくい
BtoB企業は、法人との長期的な取引を軸に、事業が展開されるのが特徴です。取引相手は企業となるため、数年にわたり事業取引が継続されることも珍しくありません。安定的な取引企業が多いと、相対的に個人消費の変動を受けにくい傾向があります。
また、事業内容によってはアフターサービスや定期発注など、継続収益を生む仕組みを持つ会社も多くあります。例えば、クラウドサービスを提供するIT企業や、部品を供給するメーカーなどは、契約更新によって安定した売上を維持しています。
これらのことを考えると、BtoB企業は景気の変化に左右されにくい特徴があるといえるでしょう。じっくり経験を積みながら力を発揮したい学生にとって、安心して成長できるフィールドかもしれません。
社会や産業の根幹を支えるやりがいがある
BtoB企業の製品やサービスは、社会の土台を支える重要な役割を担っています。例えば、インフラが止まれば社会全体に影響が出ることが多く、物流が止まれば店舗の棚に商品が並ばなくなるかもしれません。こうした「当たり前の日常」を守っているのがBtoBの仕事です。
一見すると目立たないかもしれませんが、BtoB企業が提供するサービスや商品は、まさに「社会を支えている」といえるでしょう。目立つ華やかさより、「誰かの生活を支える喜び」を感じたい人には、BtoB分野での仕事が向いているかもしれません。
専門知識を深めて長期的にキャリアを築ける
BtoBの仕事では、取引先や市場課題を分析しながら、最適な提案を行う必要がありますが、その過程では「専門知識や分析力」「課題解決力」などが少しずつ身についていきます。例えば、営業職なら課題を見つけて解決策を提案する力、技術職なら業界特有の技術や運用ノウハウが磨かれるでしょう。
取引先との関係が長く続くBtoBでは、積み重ねた経験がそのまま自分のキャリアとなるため、長期的な目線で自己成長を感じる場面も多いでしょう。メーカー、IT、通信など業界を問わず、専門性を磨きながら長く活躍したい人に向いているビジネスモデルといえます。
dodaキャンパスの就活軸診断では 【所要時間5分】であなたが大切にしている価値観を言語化!診断結果はそのままキャリアノートに反映することができるので、あなたの大切にしたい軸に合った企業からオファーが届きやすくなります。

BtoB企業の弱点
BtoBの仕事はやりがいが大きい一方で、すぐに成果が見えにくかったり、エンドユーザーの反応を感じにくい場面もあります。また、事業を進めるうえでは関連する部署も多く、調整が必要になることも多いでしょう。
ここでは、BtoB企業で働くうえでのデメリットについても見ていきましょう。
成果が出るまで時間がかかる
企業同士の取引では、契約や導入までに複数の部署が関わり、長期間検討が重ねられるため、「すぐに成果を感じられない」というデメリットがあります。事業規模にもよりますが、提案から受注まで数ヶ月〜数年に及ぶことも少なくありません。
長期的に顧客と信頼を築きながら、成果を積み上げていきたいタイプに向いている環境といえるでしょう。
消費者の反応が見えにくく実感を得にくい
BtoBの取引相手は企業であり、最終的な利用者は一般消費者であっても距離があります。そのため、自分の仕事が社会のどこで役立っているのか、実感しづらい瞬間もあるでしょう。
テレビCMやSNSで注目を集めるような企業と比べると、派手さがないと感じる人もいます。とはいえ、BtoB企業の多くは社会や産業の仕組みを支える存在です。目立たないところであっても、「自分の仕事が誰かの活動を支えている」という誇りを感じられる仕事といえるでしょう。
顧客対応が複雑で高い調整力が求められる
BtoBの現場では、顧客企業の購買部門、技術部門、経営層など、さまざまな立場の人と関わりながら仕事を進める必要があります。案件によっては思い通りに進まず、部署間の調整が必要になることもあります。
関係者の意見をまとめるには、細やかなコミュニケーションを重ねて信頼を築く力が求められます。そのため、人とじっくり話すより一人で進めたいタイプや、スピード感を重視する人はストレスを感じることがあるかもしれません。
反対に、調整や交渉を通じてチームで成果をつくることにやりがいを感じる人には、BtoBはやりがいの大きい環境といえるでしょう。

自分に合った働き方がわからないという人はdodaキャンパスのキャリアタイプ診断をやってみてくださいね。

BtoB以外のビジネスモデルも知っておこう
ビジネスモデルには、BtoB以外にも「企業が個人に販売するBtoC」「消費者同士が取引するCtoC」「行政と関わるBtoG」など、さまざまなパターンがあります。業界研究や企業選びをするうえでは、それぞれの違いも把握しておきましょう。
BtoC(企業対消費者)
BtoCは「Business to Consumer」の略で、企業が個人の消費者に直接商品やサービスを提供する仕組みを指します。コンビニ、アパレル、飲食、家電メーカー、動画配信サービスなど、日常生活でよく目にする企業の多くがこの形です。
CtoC(消費者同士の取引)
CtoCは「Consumer to Consumer」の略で、消費者同士がモノやサービスを直接やり取りする取引モデルを指します。代表例としては、メルカリなどのフリマアプリや、スキルシェアサービス(例:ココナラ、タイムチケットなど)が挙げられます。
取引の仲介役としてのプラットフォームを運営する企業も多く、最近では新しいビジネスモデルとして急速に拡大しており、スタートアップやIT業界に関心のある学生に人気です。
BtoG(企業と官公庁の取引)
BtoGは「Business to Government」の略で、企業が官公庁や自治体などの公共機関に製品やサービスを提供するビジネスモデルを指します。たとえば、行政システムの開発、道路や公共施設の建設、防災設備の導入などが代表的な例です。

BtoBに関するよくある質問(FAQ)
「BtoBってよく聞くけど、結局どういう意味?」そんな疑問を持つ就活生も少なくありません。ここでは、BtoBの基本的な意味や、BtoCとの人気の違いまで、よくある質問をまとめました。
Q:「BtoBは何の略?わかりやすく言うと?」
A:BtoBは「Business to Business」の略で、企業と企業の間で商品やサービスを取引することを指します。たとえば、部品メーカーが自動車メーカーにパーツを納める、IT企業が企業向けにシステムを提供する——こうした関係がBtoBの典型です。「B2B」も同じ意味で使われます。
Q:「BtoB営業とはどんな仕事?」
A:BtoB営業は、相手企業の課題を聞き出し、最適な解決策を提案する「課題解決型営業」が中心です。求められるのは、ヒアリング力と提案力。相手のことを考えながら、粘り強く交渉できるタイプがBtoB営業には向いています。
Q:「BtoBとBtoCどちらが就活で人気?」
A:一般的に、BtoC企業はテレビCMやSNSなどで目にする機会が多く、知名度の高さから就活生の人気が集中する傾向があります。一方で、BtoB企業は専門性や安定性の高さが評価される分野です。名前が知られていないだけで、社会や業界を支える人気企業は数多く存在します。
知名度だけで判断せず、自分の強みを生かせる企業はどこなのかを慎重に検討すると良いでしょう。
BtoBを理解して就活の選択肢を広げよう
BtoBの意味や仕組み、BtoCとの違いがわかれば、業界や企業選びも進めやすくなります。社会基盤を支える役割を担っているのが、BtoBのビジネスです。
就活では、イメージだけで企業を選ぶのではなく、「社会や顧客にどのような価値を提供しているか?」「自分の価値観に合う企業はどこなのか」に注目してみてください。きっと自分が活躍できるステージが見つかるはずです。
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
関連記事
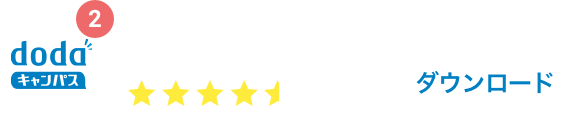



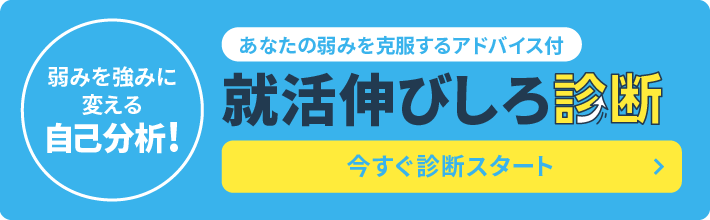
 シェア
シェア