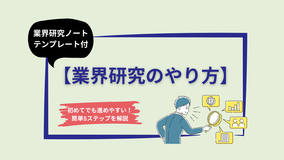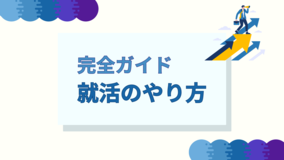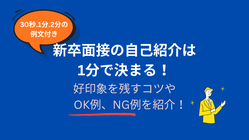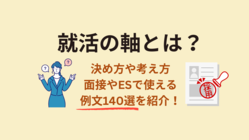就活では、業界や企業選びはもちろん「職種選び」も重要なポイントです。
「どんな職種で活躍したいのか?」をはっきりさせておくと、将来歩むべきキャリアの方向性も明確になります。ただ、就活を進めていると「職業と職種は何が違う?」など、用語の理解が進まず混乱してしまうこともありますよね。
今回は、職種とは何か?といった基本をはじめ、業種や職業との違い、自分に合った職種の見つけ方について詳しく解説!
自分の強みが活かせる職種を見つけて、就活を成功させましょう。
「職種も大事だけど、そもそも志望する業界が定まらない」と悩むなら、dodaキャンパスの「業界研究ファイル」をダウンロードしてみませんか?人気12業界の業界動向やビジネスモデルなど、さまざまな業界理解が進む資料が無料で受け取れます。求められる人物像も理解できますので、興味がありそうな業界から情報を整理してみましょう。
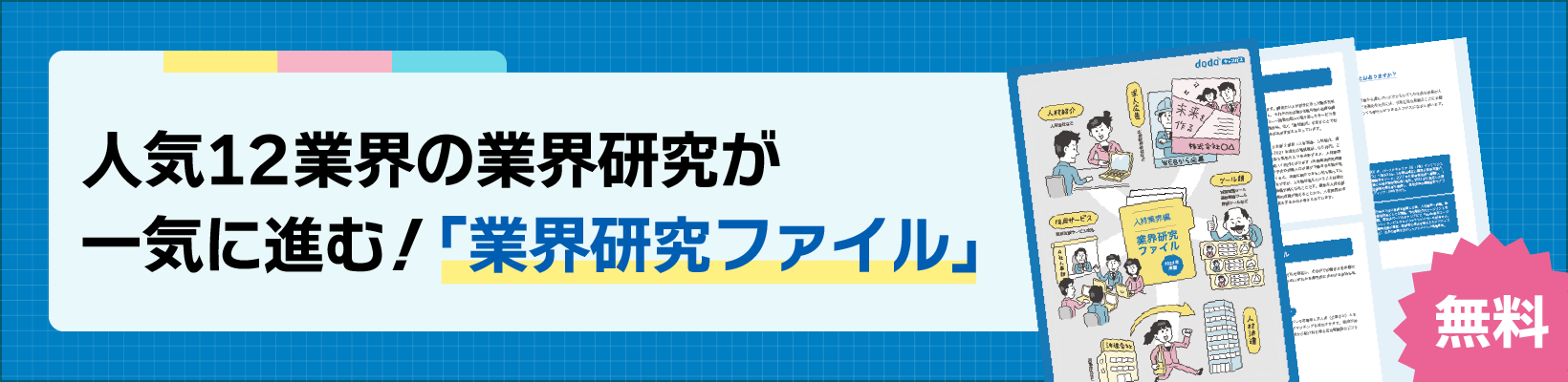
目次
職種とは?業界や業種、職業との違い
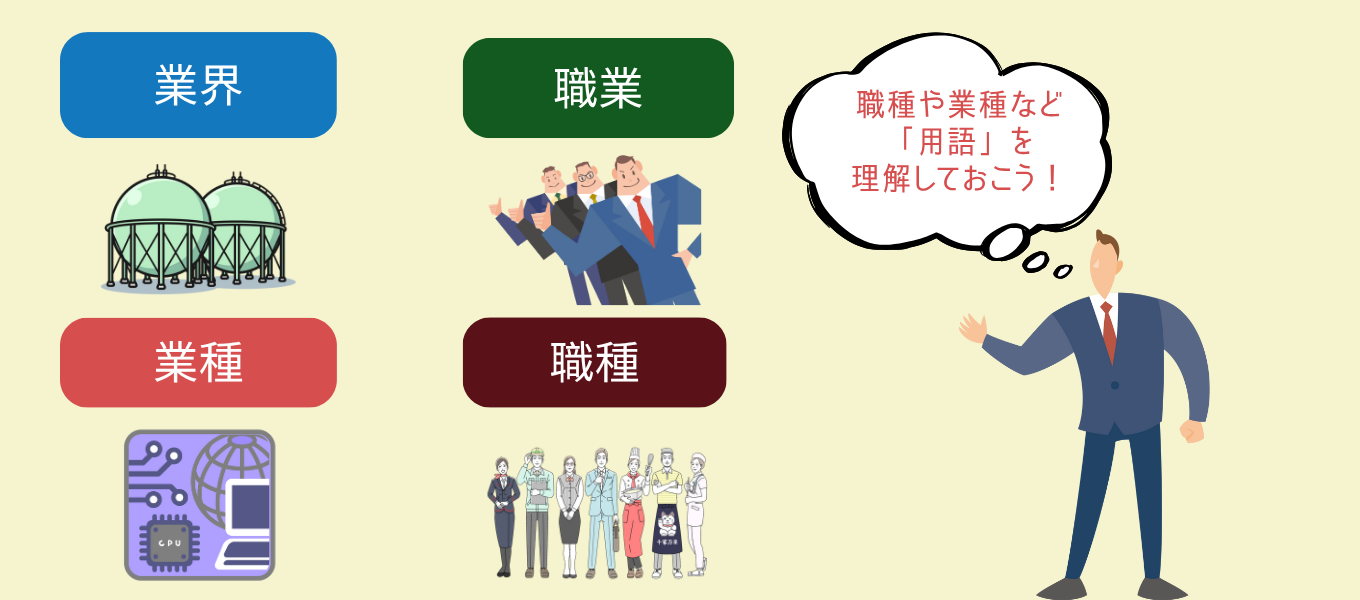
就活で戸惑いがちなのが、「業界」「業種」「職種」といった言葉の違いです。まず、それぞれの用語の違いから整理していきましょう。
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 業界 | 企業が属するビジネスの分野 | IT業界、製造業界、金融業界 |
| 業種 | 企業が営む事業の種類(分類) | ソフトウェア(ソフトウエアとも表記)業、食品製造業など |
| 職業 | 社会的な役割や働き方全体 | 公務員、会社員など |
| 職種 | 個人が担当する仕事の種類 | 営業、経理、エンジニア、人事、研究職など |
入社する企業は同じでも、職種別で必要なスキルや働くスタイルも違ってきます。就活では、業界や企業選びも重要ですが、「どんな職種に就き、どのように活躍したいのか?」を明確にしておきましょう。
職種選びでは、自己分析が重要。5分で完成!AIがあなたの強みを分析してくれる無料のサービスをご存知ですか?「自分がどんな職種に向いているのかわからない」と悩んでいるなら、ぜひ試してみてください!自分が気づいていない意外な強みが見つかるかもしれません。
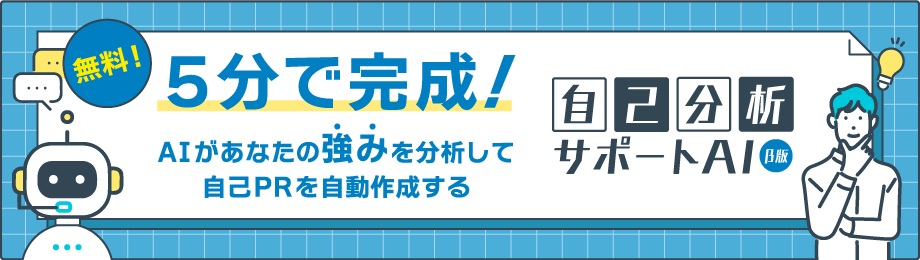
自分に合った仕事がわかる!職種の調べ方

就活では、知っている仕事だけを見るのではなく、「こんな仕事もあるんだ」と広く見てみることが大切です。先入観にとらわれず、さまざまな職種をざっくり調べてみましょう。
先入観で職種を判断すると、仕事内容やスキルを誤解し、入社後のミスマッチや選考での失敗につながる恐れがあります。
厚生労働省のサイトや企業の新卒採用サイトを活用し、世の中にどのような職種があるのか調べてみましょう。
厚生労働省サイトでリサーチする
厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」には、約600以上の職種が掲載されているだけではなく、その職種に求められるスキルや、将来のキャリアパスといった理解も得られます。
厚生労働省のjobtagで得られる情報
- 主な仕事内容
- 労働条件
- 必要な知識・スキル・資格
- 働き方やキャリアパス
また、厚生労働省のPDF版の職業分類表には全職種が網羅されており、職種を比較検討したいときに便利です。自分が知らない、意外な職種に出会えるかもしれません。
企業の新卒採用サイトで調べる
企業の新卒採用サイトで、職種を調べる方法もあります。企業によっては下記のような具体的な情報も得られるため、社会人になってからの働き方もイメージしやすいでしょう。
- その職種のミッションや担当業務
- 一日の業務スケジュール
- キャリアのステップ(新人~リーダーに昇格するまでのイメージ)
- 先輩社員のインタビュー
複数企業の採用ページを比較してみると、「同じ職種でも企業によって役割が違う」といった点にも気づくはずです。入社後のミスマッチを避けるためにも、より多くの情報を見て比較検討してみましょう。
「自分に合う企業がわからない」という方は、あなたを魅力に感じた企業からオファーが届くスカウト型就活サービス『dodaキャンパス』がオススメ。早期選考などの特別オファーももらうことができるため、ぜひ登録しておきましょう。

就活でチェックしておきたい代表的な職種一覧
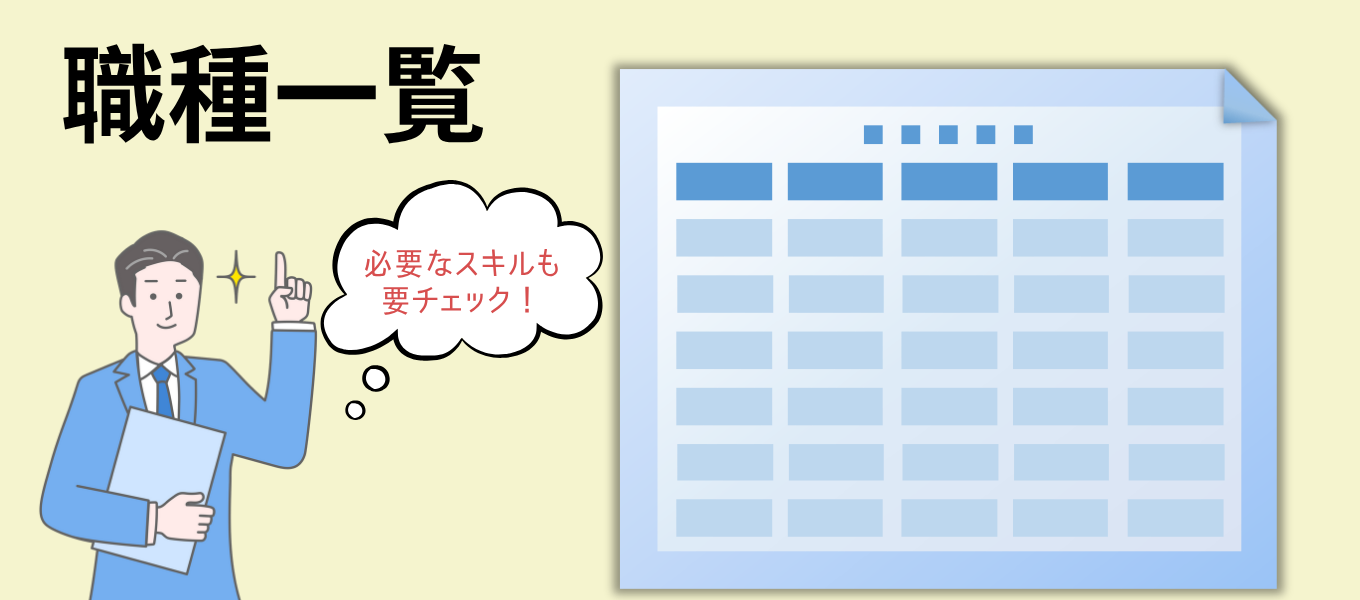
職種選びの第一歩として、厚生労働省の公式サイトから代表的な職種をピックアップしてみました。求められるスキルや、その職業に就ける代表的な業界なども整理していますので、業界研究や企業研究と一緒に職種選びも進めてみましょう。
※職種名は編集部にて一般的に呼ばれる名称に編集しています
参考出典:職業情報提供サイトjcb tag
営業、販売系の職種一覧
営業や販売系の職種は、企業の売上をつくる役割を担います。交渉能力だけではなく、自社の商品やサービスを通じ、顧客課題を解決する能力が求められる職種です。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 商社営業 | 国や地域、企業の間に立って、原材料や製品の売り買いをする | 傾聴力、課題発見力・提案力 |
| 証券外務員 | 株式や投資信託などの商品を投資家に提案する | |
| ITコンサルティング営業 | 情報システムや情報サービスを通じ、顧客課題を解決する |
ほとんどの企業には営業職として活躍できる部署がありますが、代表的な業界としては「商社」「金融機関」などがあります。
技術、開発系の職種一覧
技術・開発系の職種は、「ものづくりの中核」を担います。高度な専門知識とスキルが求められ、経験がそのまま自身のキャリアにもつながる職種です。IT化や自動化が進む中、技術者には高い柔軟性と学び続ける姿勢も求められるでしょう。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 電気技術者 | 電気設備や機器の技術開発。保守・管理、更新工事などを行う | 専門知識、課題発見力、分析力 |
| システムエンジニア | 情報システムの開発を受託し、ソフトウェアやシステムを構築する | |
| 半導体技術者 | 半導体製品の製造工程の設計・開発、評価等を行う |
技術・開発系の職種に就くには、メーカーやIT企業・インフラ企業・研究機関などへの就職が一般的です。
事務系の職種一覧
事務職は企業運営を支える裏方的な存在ですが、正確性や効率性・社内調整力などが求められる職種です。業務の効率化や社内の仕組みづくりにも関わるため、柔軟な思考やITスキルも求められるでしょう。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 一般事務 | さまざまな定型事務作業を行う | 正確性、課題発見力、調整力、コミュニケーション能力 |
| 医療事務 | 外来の受付、医療費の請求、入退院の手続などを行う | |
| 経理事務 | 企業の入出金、社内の資金管理、給料の支払等を行う |
事務職はほとんどの企業で募集されていますが、代表的な業界としては、メーカー・金融機関・商社・IT・官公庁などが挙げられます。
サービス系の職種一覧
サービス系の職種は、顧客と直接接点を持ち、商品やサービスを届ける役割を担います。接客力だけでなく、商品知識や観察力、協調性なども求められるでしょう。
サービス系の職種では、人と接する仕事を通じて「顧客体験の質」を高めることが求められます。顧客ニーズをくみ取る力や、臨機応変な判断力が必要な職種です。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| メイクアップアーティスト | メイクアップ技術を駆使し、人をより美しく演出する。 | 商品知識・提案力・ホスピタリティ |
| パティシエ | 洋菓子店や菓子工場で洋菓子を製造する | |
| 客室乗務員 | 航空機内で乗客の世話など様々なサービスや緊急時の保安対応を行う |
サービス系の職種に就くには、飲食・観光・美容・航空・小売など、サービス業全般を展開する企業への就職が一般的です。
管理、企画系の職種一覧
管理・企画系の職種は、企業の戦略立案や制度設計など、企業の中枢の役割を担います。企業の将来を左右するテーマを扱うこともあるため、論理的思考力やデータ分析力に加え、柔軟な発想力や対人調整力も求められます。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 商品企画 | 消費者のニーズを掴み、販売見込みの高い商品を企画開発する | 課題発見力、論理的思考、発想力、調整力 |
| Webマーケター | Web技術を利用してマーケティングを行う | |
| バイヤー | 店舗で扱う商品を仕入れる。販売戦略を考えたり、生産者と一緒に商品を開発することもある |
総合職の募集がある企業であれば、ほぼ管理や企画系の職種にも就けるでしょう。企業の意思決定に関わる業務も多いため、実務経験や経営視点を持って行動できるかどうかもポイントです。
クリエイティブ系の職種一覧
クリエイティブ系職種は、デザインや編集などの仕事を通じ、人の心を動かす役割を担います。美的センスや発想力だけでなく、ユーザー視点やコンセプト設計力も求められる職種です。また、納期や予算などの制約の中で成果を出すためのマネジメント力や、コミュニケーション力も重要です。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| UX/UIデザイナー | Webサイトや電子機器において、ユーザーが使いやすいインターフェースを設計し、デザインする | デザイン力、企画力、文章力、調整力 |
| テクニカルイラストレーター | 工業製品のマニュアルなどに使う、視覚的にわかりやすい説明や立体図などを作成する | |
| Webデザイナー | 企業、学校、官公庁などがインターネット上に設けたWebサイトの企画・デザイン等を行う |
クリエイティブ系の職種を希望するなら、広告代理店や出版社、Web制作会社やメーカーの企画部門などをチェックしてみましょう。近年はIT系企業やスタートアップでもクリエイティブ職の活躍が広がっており、業種を問わず多様な分野での活躍も期待できます。
製造系の職種一覧
製造系の職種は、現場でのモノづくりや品質管理、生産工程の管理などに携わります。安全性や効率を追求する視点と、単調な作業をこなす几帳面さも必要です。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 医薬品製造 | 製造ラインを運転し、医薬品を製造する | 観察力、正確性、忍耐力 |
| 化学製品製造オペレータ | 化学肥料、化学繊維、洗剤、塗料などの化学製品を製造する | |
| 半導体製造 | 設備、装置、機械を操作、監視し半導体を製造する |
製造系の職種は、自動車・電機・化学・食品・繊維などのメーカーなどで募集されています。工場勤務だけではなく、設計や検査、生産技術などにも携わるため、どのような職種が自身の適性に合いそうか、よく見極めることが重要です。
公共、教育系など公務員の職種一覧
公共、教育系の職種は、社会全体や地域の人々の生活を支える仕事です。安定した職場環境の中で、人の成長や社会の基盤づくりに関われるのは、大きな魅力といえるでしょう。ただし、公的なサービスを提供するため、責任感や高い倫理観が求められる職種です。
| 職種名 | 業務内容 | 求められるスキル |
|---|---|---|
| 教員 | 専門の教科を教え、生徒を指導する | 対応力、調整力、企画力、コミュニケーション能力 |
| 国家公務員(行政事務) | 行政機関に勤務し、行政の事業が円滑に進むよう運営する | |
| 地方公務員(行政事務) | 地方自治体に勤務し、行政施策の企画・立案、予算の編成から実際の業務までを担当する |
公共・教育系の職種に就くには、国家公務員・地方公務員の採用試験や教員免許の取得が必要です。勤務先は国の省庁や出先機関、市町村役場、公立学校など多岐にわたり、「地域社会貢献したい」という志を持つ人に向いています。
自分に合った業界・職種の選び方

職種を選ぶ際は、「なんとなく」ではなく、自分の価値観に合った職種を探す「軸」を持っておくことが重要。そのためには、自己分析の結果を言語化し、職種に関する情報を広く集めた上で比較検討する必要があります。
1.自己分析をする
自己分析では、自分の価値観や強み、興味関心(どんなことにワクワクするか)などを掘り下げていきます。自己分析を重ねていくと、「どんな職場なら力を発揮できそうか」「どんな仕事にやりがいを感じるか」など、自分なりの軸が見えてくるでしょう。
例えば、「人の役に立ちたい」という価値観を持っているなら、医療や教育、福祉系の職種が向いているかもしれません。「論理的に考えるのが得意」という強みを持つ人は、システムエンジニアや研究職が候補に挙がるでしょう。職種選びの軸が明確になると、志望動機にも一貫性が生まれ、選考でも説得力が増します。
「自己分析」は主観が入りがちなため、一人でもくもくと作業していてもなかなか客観的な分析が難しいものです。。dodaキャンパスの「自己分析サポートAI」であれば、AIがあなたの強みを客観的に分析。自己PRも自動作成するため、一石二鳥で役立ちます。
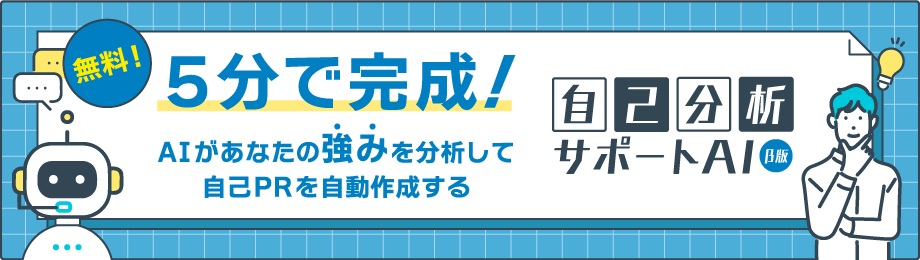
2.業界や職種について調べる
自己分析で方向性が見えてきたら、世の中にどんな職種があるか調べましょう。職種をリサーチする時は、はじめから「この職種が向いていそう」など先入観を持たず、広く情報を集めることが重要です。
また、「同じ職種でも業種によって仕事内容や働き方が異なる」ことにも注目しましょう。例えば、同じ営業職でもIT業界と不動産業界では、求められるスキルは大きく異なります。このような違いを理解しておけば、ミスマッチも防げるでしょう。
3.インターンシップで情報収集する
インターンシップは、実務を体験できる貴重な機会です。会社説明会や企業の公式サイトだけではわからない、仕事の進め方なども肌で感じることができます。先輩社員とのコミュニケーションを通じて、実際の仕事で得られる「やりがい」を感じられる点は、大きなメリットです。
インターシップで情報収集する際は、できるだけ複数の業種や職種を経験すると良いでしょう。「この仕事は想像以上に面白かった」「自分に向いていると思ったが実は違った」など、新たな気づきが得られます。
インターンを通して得られた経験は、そのままエントリーシートや面接でのエピソードにも生かせるためおすすめです。
4.集めた情報や得た経験をもとに比較検討する
最後は、自分が集めた情報や実体験をもとに比較していくわけですが、ここでは下記3つのポイントを意識しましょう。
- やりがい:その職種は誰の役に立ち、どのような価値を生み出すのか?
- キャリア:その職種を続けていけばどのようなスキルが磨かれるのか?目標にしたいキャリアは積めそうか?
- ライフスタイル:自分の望む働き方(勤務地・残業・柔軟性など)と合っているか?
「その仕事にワクワクできるか?」「続けたいと思えそうか?」という感覚も大切にしましょう。納得感があるからこそ、入社後もブレずに頑張ることができます。

自己分析で見えた強みを活かして、企業からのオファーを受け取ろう!
数多くの業界や職種の中から、自分に合うものを選択するのは難しいですよね。しかし、業界・業種と同様、職種も納得の就職先を選ぶために重要な要素の一つです。
ぜひ、この記事で紹介した内容を参考に、自分に合う職種について考えてみてください。
もし「自分に合う企業と効率的に出会いたい」と考えているのであれば、ベネッセの就活支援サービス『dodaキャンパス』を利用してみませんか?
プロフィールや希望条件を設定しておけば、あなたの希望に合った企業から直接オファーが届きます。まだ活用していないという方は、ぜひ使ってみてください!
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
関連記事
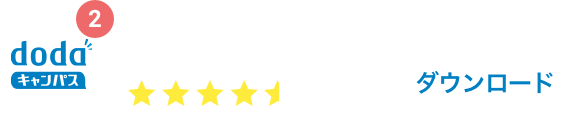

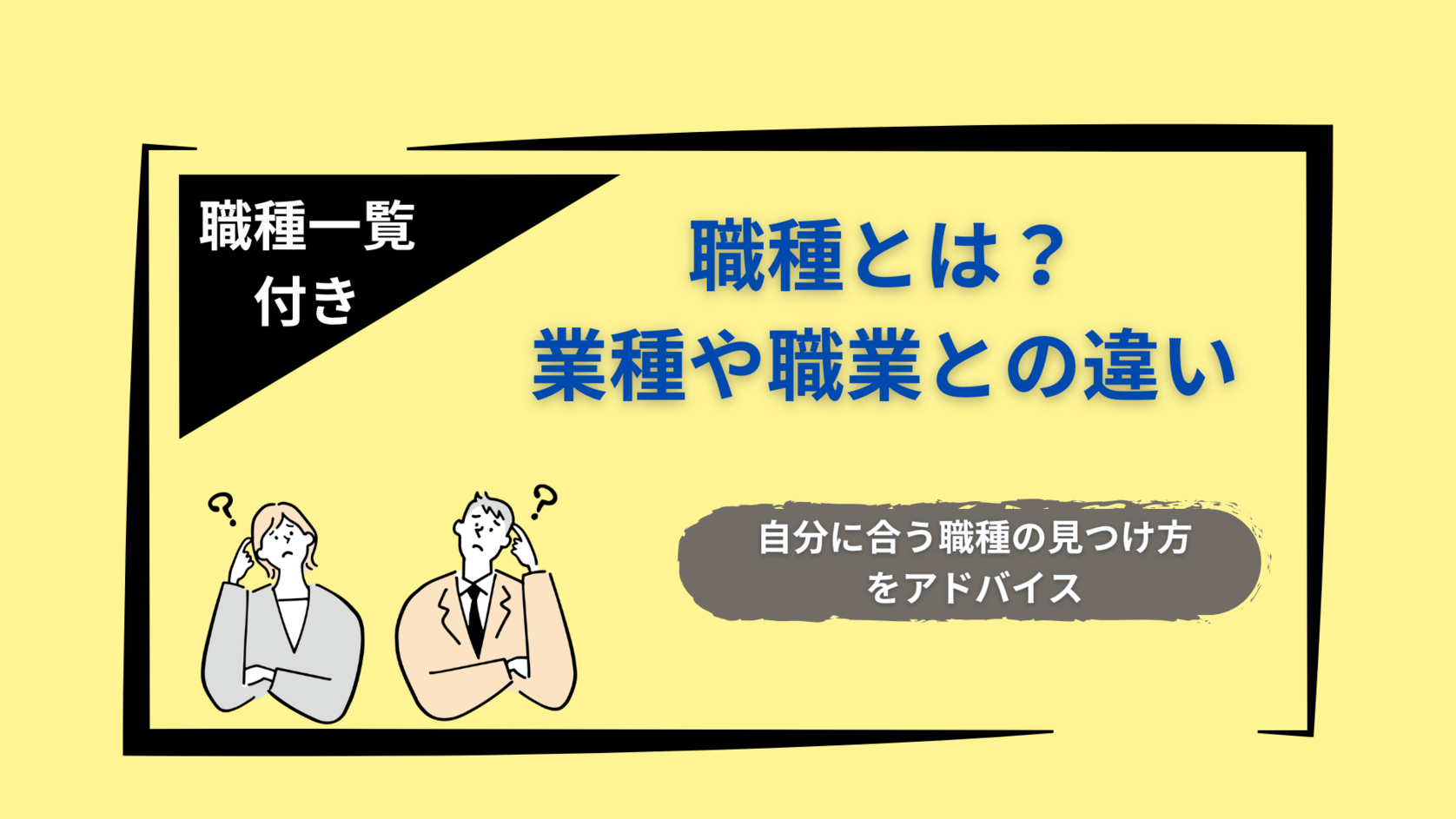

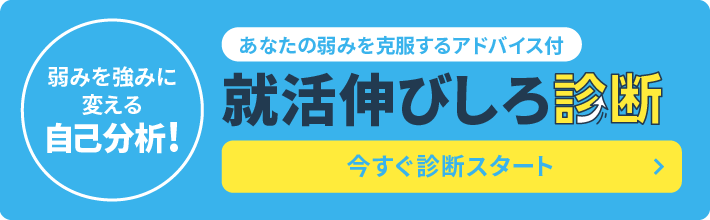
 シェア
シェア