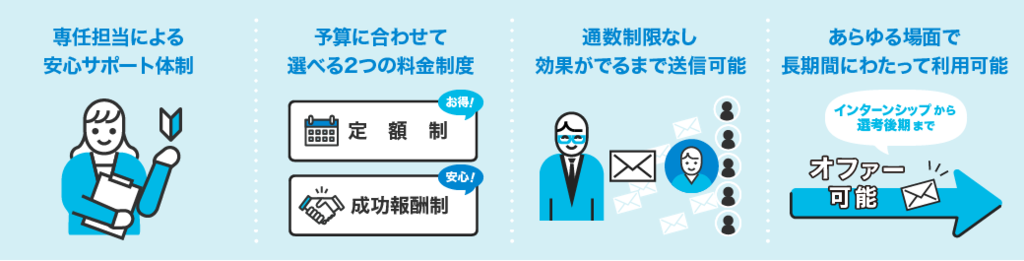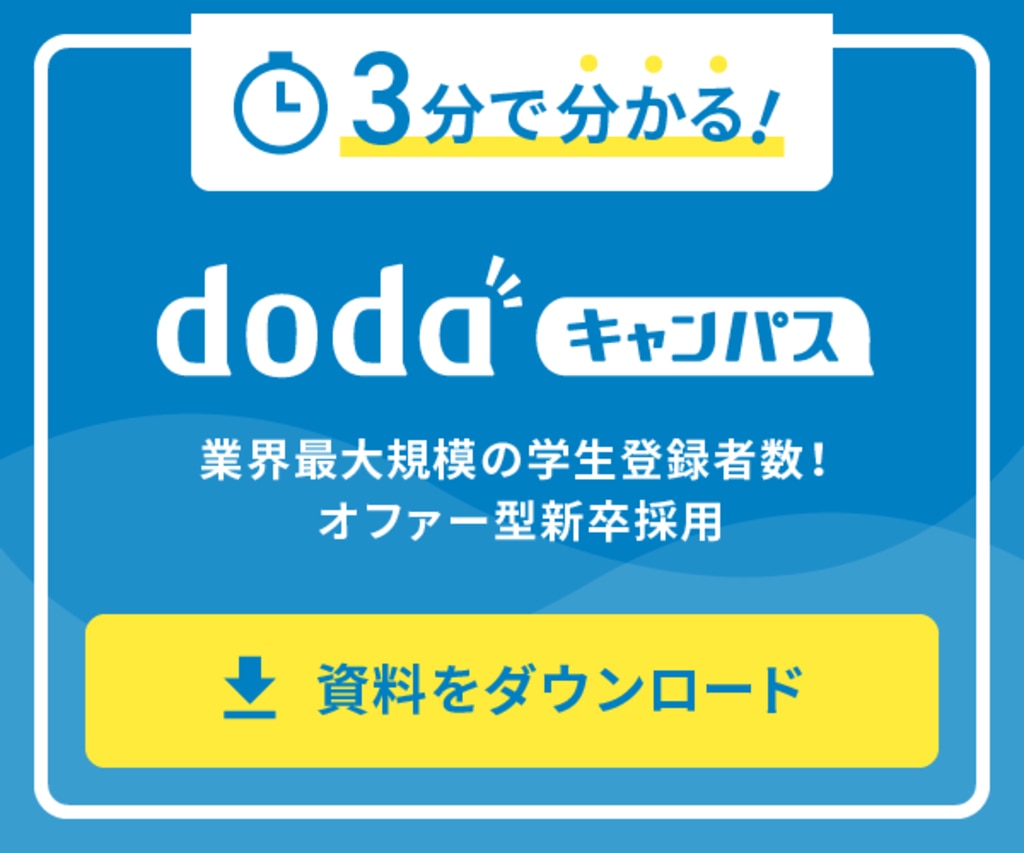採用活動の進め方!内定までのスケジュール、ポイントについて解説
採用活動の強化を図るために採用計画の見直しを検討しているものの、自社に合う効果的な方法が見つからず悩んでいる採用担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、効果的な採用手法や採用活動のポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
▼関連資料
採用活動とは?

採用活動とは、自社が求める人物像に合った人材を採用するための活動です。明確な目的や準備もなく闇雲に行っても、思うような成果は得られないでしょう。ここでは、採用活動を始める前に必要な準備と採用活動の目的を解説します。
採用活動前の準備
採用計画は、事業計画に沿っているのかを検討する必要があります。事業計画は企業として目指すべきビジョンをまとめたものです。採用計画は自社のビジョンを達成するために逆算して、どのような人材がどれくらい必要なのかを明確にしましょう。
採用活動を行う目的
採用活動は、現場の人手不足を補う目的で実施されるわけではありません。本来の目的は自社が目指すビジョンの実現や目標達成のために必要な人材を確保することにあります。採用計画をもとに戦略的に採用活動を行うことで、事業計画で定めたビジョンや目標の達成につながります。
採用活動の流れ

続いて、新卒採用スケジュールを立てる際の具体的な作成方法やポイントを見ていきましょう。
1.採用したい人材のターゲット像を決める
まず採用活動では、どのような学生が自社にマッチするのかを洗い出し、ターゲットとなる学生の要件をまとめましょう。
ターゲットが明確でない場合、入社後のミスマッチや選考辞退・内定辞退を招く恐れも。採用計画やコストを無駄にしないためにも、ターゲットを詳細に設計することが大切です。
>>>押さえたいポイント!
ターゲットを設計する際は、実在するような1人の学生が想像できるぐらいまでイメージを具体化させましょう。価値観やライフスタイル、行動特性などの情報を具体化させるのがオススメです。
また、経営層と現場社員へのヒアリングを行い、社内で活躍する社員の行動特性や特徴を洗い出しておくと、採用のミスマッチを防ぐ採用活動ができるでしょう。
▼関連資料
『効率的な採用活動を実現するためのターゲット設計 5ステップ』
2.採用戦略を立てる
次に、採用に向けた戦略を立てましょう。
売り手市場が続くなか、企業が優秀な学生を獲得するためには、自社の強みを把握し、学生にアピールすることが重要なポイントです。
特にアピールすべき項目は下記の通りです。
- 自社の知名度
- 企業規模や市場
- 扱う商材の魅力や独自性
- 競合他社と比較した自社の強み
- 社風
- 業務内容や働き方
- 社内制度や福利厚生
これらの項目について自社を分析し、学生にアピールしたいポイントや、具体的なアプローチ手法を検討しましょう。
>>>押さえたいポイント!
採用活動では「競合他社や大手企業と差別化できているか」「ターゲットに合ったアプローチができているか」といった点を意識しましょう。
自社の強みをしっかりと把握できていれば、採用サイトや自社サイトに盛り込むコンテンツ、学生へのメッセージ内容なども、スムーズに考えられるはずです。
3.採用したい学生のスケジュールや他社の動向を把握する
採用戦略をもとに、具体的な採用スケジュールを作成します。
採用スケジュールを組む際は、下記に記載した項目に関する「各フローの日程」「必要となる対応」を明確にすることがポイントです。各プロセスで資料作成や会場予約といった準備が必要となるため、最終的な内定出しのタイミングから逆算すると良いでしょう。
- インターンシップ
- 広報活動
- 会社説明会
- 採用選考活動
- 内定出し
>>>押さえたいポイント!
採用スケジュールは、企業規模や業種によって異なります。ターゲットとなる学生の就活スケジュールや、他社の動向も踏まえて時期を検討しましょう。
特に中小企業の場合は、競合となる大手企業と時期が重ならないよう、選考時期を前後にずらすケースも。あえて後ろ倒しで採用活動を行う場合もありますので、競合他社の状況についても把握しておきたいところです。
▼関連記事
『【セミナーレポート】地方×中小企業でも学生をグリップし続ける早期選考術 』
4.採用手法・ツールを選定する
広報活動開始 ・ 採用選考活動開始・内定出しなどのスケジュールが決まったら、具体的な採用方法・ツールについて考えましょう。
一般的な採用手法は、下記の様なものが挙げられます。
- ダイレクトリクルーティング
- ナビサイト
- 新卒紹介サービス
- 合同説明会・就活イベント
- 自社ホームページにおける採用サイト
- ソーシャルリクルーティング
- ミートアップ
>>>押さえたいポイント!
ナビサイトや合同説明会などで接点を持った学生は、その後企業のホームページもをチェックします。「Webサイトの制作に力を入れているかどうかを見ている」といった学生も存在するため、自社ホームページに加えて独立した採用サイトを用意しておくのも効果的です。
▼関連資料
5.内定後のフォロー体制を構築する
新卒採用の活動は、内定を出して終了ではありません。
内定辞退を防ぎ、入社意思を固めてもらうためには、学生の不安を払拭し自社に興味を持ち続けてもらう必要があります。そのため、継続的なフォローが肝心です。
スケジュールを策定する際に、内定後のフォローをどのように実施するか、社内体制を構築しておきましょう。
内定者へのフォローは、下記のような取り組みがあります。
- 内定者研修
- 採用担当者(教育担当者)との面談
- 社員との懇親会(食事会、座談会、社内イベントなど)
- 職場見学
- 内定者同士のコミュニケーションの場
- 内定者インターンシップ
- リクルーターをつけて適宜相談に応じる
>>>押さえたいポイント!
売り手市場が続く中、「自分を求める企業で働きたい」という声が聞かれるようになっています。採用活動において継続的なコミュニケーションは人材を大切にしている企業であることを知ってもらうだけでなく、学生に対する期待やあなたが必要ですという意思表示でもあります。
気軽なコミュニケーションが取れる体制や継続性といったことをポイントに、内定者フォローの方法を検討されると良いでしょう。
▼関連資料
辞退を未然に防止するための内定者フォローのポイント
効果的な採用手法

採用活動にはさまざまな方法があり、自社に合ったものを選択する必要があります。ここでは、効果的な採用手法を紹介します。
Web(オンライン)面接
Web(オンライン)面接とは、オンライン上で行う面接です。Web(オンライン)面接のメリットは応募者の都合に合わせて日程を決めやすく、面接官の育成にも役立つ点です。
ただし対面で面接するよりも相手の表情が読み取りにくく、通信環境によっては面接中に接続が切れるといったトラブルが起こりやすいので、事前に通信環境を確認しておく必要があります。
ソーシャルリクルーティング
ソーシャルリクルーティングとは、SNSを活用した採用手法です。ソーシャルリクルーティングが注目されている理由は、日常的に利用されているSNSを通じて積極的にアプローチできるからです。
ソーシャルリクルーティングのメリットは、採用コストの削減や入社後のミスマッチの防止などです。ただし、効果が出るまでに時間がかかるため、長期的な視点を持って取り組みましょう。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社の社員の友人・知人を紹介してもらう採用手法です。採用活動で多くの企業がリファラル採用を導入する理由は、従来の採用手法のみでは人材の獲得が難しくなってきているためです。また、社員を通じて自社の魅力や職場の雰囲気などのリアルな情報を伝えやすくなることも理由の一つです。
リファラル採用のメリットは、自社をよく理解した信頼性の高い社員が紹介する転職潜在層の人材にアプローチできることです。さらに、入社後のミスマッチがないのでエンゲージメントの向上にもつながります
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、企業が応募者に直接アプローチする採用手法です。ダイレクトリクルーティングのメリットは、採用活動を効率的に行えることです。デメリットは、採用担当者の業務負担が増える点です。
採用活動のポイント

採用活動を成功させるためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。主なポイントは以下の3つです。
- 事業計画を基盤とする
- 求める人物像を明確に
- 面接官の育成
事業計画を基盤とする
採用活動を成功させるためには、事業計画をもとに人事戦略を立てましょう。企業のビジョンを達成するためには何をするのかを示したのが「事業計画」で、事業計画を具体化したものが「組織戦略」です。事業計画に基づいて採用活動を行うことで、採用のミスマッチを避けられます。
求める人物像を明確に
自社が求める人物像を明確にしておくことも採用活動を成功させるためのポイントです。例えば、経歴やスキル、行動特性、価値観などを考慮して人物像を明確にしましょう。求める人物像が曖昧であると採用基準がぶれるため、母集団形成に失敗しやすくなります。
面接官の育成
効果的な採用活動を行うためには面接官の育成が欠かせません。面接官の役割は、書類選考で見抜けなかった応募者の人柄や入社意欲などを見極めることです。同時に、自社の魅力を応募者に伝えて「この会社に入りたい」と思わせる役割があります。
まとめ

事業計画に基づいた採用活動を行うことで、自社のビジョンの実現に必要な人材を採用でき、企業の発展につながります。dodaキャンパスは、新卒ダイレクトリクルーティングの一種で、応募者へ直接アプローチできます。サービスを利用することで、効果的な採用活動の実現につながります。まずは以下の資料をご覧ください。