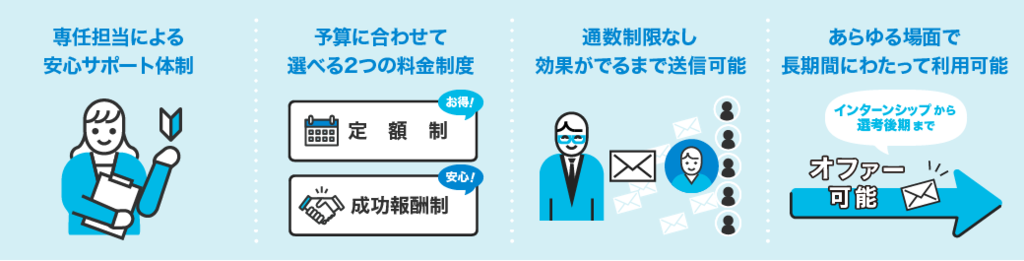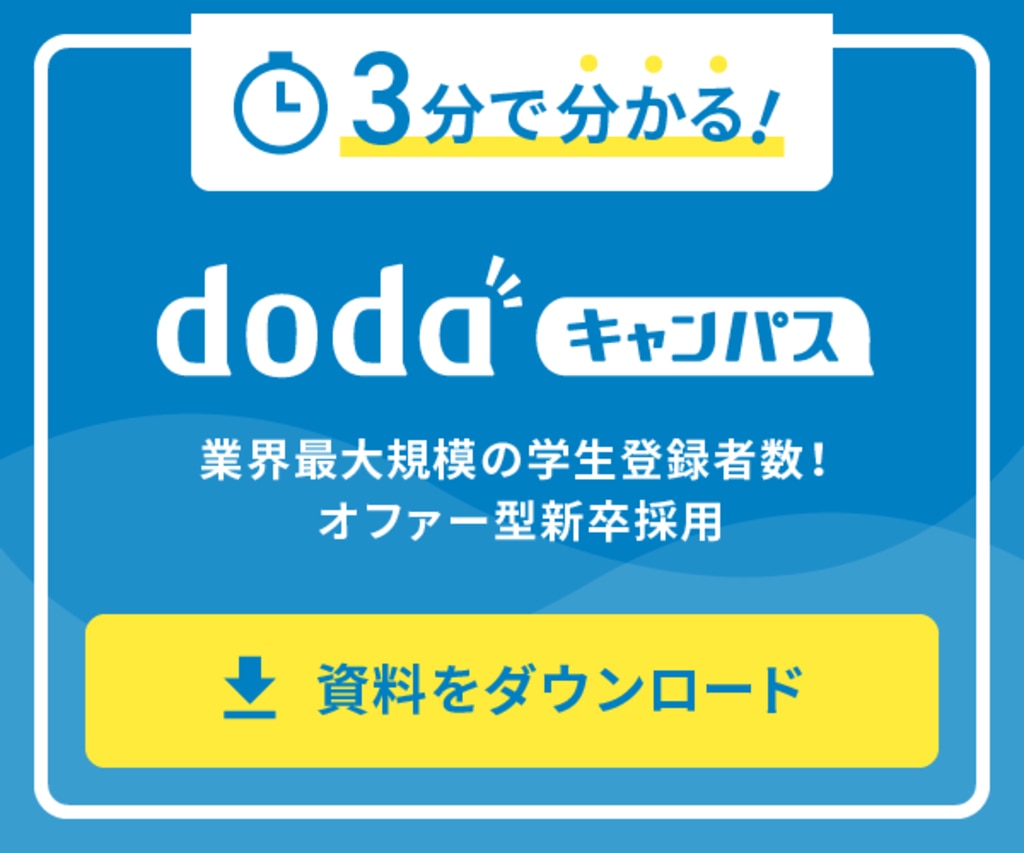【企業向け】Web説明会とは?代表的ツールや開催手順も解説
Web説明会とは、オンライン上で行う会社説明会です。採用担当者の方のなかには、Web説明会を成功させる秘訣を知りたいと考える方も多いでしょう。
この記事では、Web説明会を成功させたいと考えている採用担当者の方に向けて、Web説明会を効率的に進めるための手順やメリット・デメリット、成功させるポイントを解説します。学生を飽きさせない工夫についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
▼関連資料
【お役立ち資料】満足度を劇的に変える!会社説明会7つのポイント
目次[非表示]
- 1.Web説明会とは?いま注目される理由
- 2.Web説明会の開催方法
- 2.1.ライブ配信型説明会(ウェビナー型)
- 2.2.ライブ配信型説明会(テーブル型)
- 2.3.録画配信型説明会(オンデマンド型説明会)
- 3.Web説明会の代表的なツール
- 3.1.Zoom
- 3.2.Google meet
- 3.3.Microsoft Teams
- 4.Web説明会のメリット
- 4.1.母集団形成への貢献
- 4.2.採用コストを抑えることができる
- 4.3.参加者との対話も実現できる
- 5.Web説明会のデメリット
- 5.0.1.学生からの質問が得られにくい
- 5.1.リアルを伝えることが難しい
- 5.2.途中退室されることがある
- 6.Web説明会の実施手順
- 6.1.環境を整備する
- 6.2.資料を作成する
- 6.3.日程や服装、必要な物など学生に周知する
- 7.Web説明会の録画配信を視聴してもらうためのポイント
- 7.1.録画配信のメリット・デメリット
- 7.1.1.録画配信のメリット
- 7.1.2.録画配信のデメリット
- 7.2.録画配信のコンテンツ作成のポイント
- 7.2.1.学生からの質問に答えるプログラムを組み込む
- 7.2.2.コンテンツをセグメント分けする
- 7.2.3.最適な時間配分(30分〜1時間程度)にする
- 7.2.4.座談会形式で「社風」や「雰囲気」を感じてもらう
- 7.2.5.次のステップにつながる仕組みを作る
- 8.Web説明会を成功させるための3つのポイント
- 8.1.魅力あるコンテンツや進行を意識する
- 8.2.ライブ配信型と録画配信型の使い分け
- 8.3.面接などの次のステップへの導線設計
- 9.まとめ
Web説明会とは?いま注目される理由

Web説明会とは、スマホ・PCなどを通して、どこからでも視聴することができるオンライン上の会社説明会です。新型コロナウイルス感染症の流行やリモートワークによって、導入する企業が急激に増加しています。また、大学4年生の短期間で就活に追われる多忙な学生側にとっても、より効率的に企業を知る方法として注目度を高めています。
一方、学生が就職活動に割く時間は年を追うごとに減少しており、1人の学生がエントリーする企業数も減少の一途をたどっています。実際に就活を終えた2023年度卒業の現役社会人からは、下記のような声が聞かれました。
・説明会を聞いて何となく楽しそうな企業にエントリーしていた
・Web説明会は、他の作業をしながら聞いてることもあった
・参加のハードルが低く、期待値もそれほど高くなかった
このように直観的かつ受動的に活動する学生が増える中、企業はオンライン説明会を上手く駆使して学生から選ばれる工夫をする必要があると言えるでしょう。
採用ご担当者の方は、本記事を通して具体的な導入方法や成功ポイントを押さえ、採用成功につなげていただければ幸いです。
Web説明会の開催方法

まずは、オンライン説明会の開催方法から見ていきましょう。主流なもので分けると、3種類の方法があります。
ライブ配信型説明会(ウェビナー型)
ライブ配信型説明会とは、Web上でリアルタイムに実施される会社説明会になります。
リアルタイムで配信されるため、就活生と会話やチャットによるコミュニケーションをとることができますし、企業の説明だけでなく、社員と就活生とのコミュニケーションの場を用意することで社風や企業理解の促進につながり、意向醸成を行いやすいという特徴があります。
ライブ配信型の一つであるウェビナー型は、「ウェブ(Web)」と「セミナー(Seminar)」を組み合わせた言葉であり、ライブ配信型説明会の一種であり、ほぼ同義と言えるでしょう。
ライブ配信型説明会(テーブル型)
ライブ配信型の手法で、オンライン説明会の参加者を少人数のグループに分けてディスカッションさせる方式です。
説明会に対する主体的な姿勢を促すことができたり、ウェビナー形式と組み合わせたりすることも可能で、企業説明会後とグループワークの両方を行いたいケースに最適です。
録画配信型説明会(オンデマンド型説明会)
録画配信型説明会は、オンデマンド型説明会とも言われ、事前に録画しておいた説明会をWeb上で自由に見ることができます。
いつでも手軽に視聴することができることが最大の特徴で、忙しい就活生にとっても空き時間で閲覧することができますし、企業も作成してしまえば工数をかけずに多くの学生に説明会を実施することができる点がメリットです。
Web説明会の代表的なツール

Zoom
ズームコミュニケーションズ社が運営する企業向けの会議ツールとして有名なZoom。映像圧縮技術により比較的回線が安定しており、URLをクリックするだけで参加することができるといった魅力があります。
参加可能人数は100人~1,000人(プランによって変わります)。開催者は登録が必要で、参加数が1,000人など大規模になると有料になりますが、参加者は登録不要かつ無料で参加が可能です。
※詳細は、公式サイトをご覧ください。
Google meet
グーグル社が提供するビデオ会議サービス(旧:Google ハングアウト)。元々、ビジネス向けとして提供されていたこともあり、優れたセキュリティ性能が魅力です。
参加可能人数は100人~1,000人(プランによって変わります)。Zoomと同様、開催者は登録が必要でGoogleアカウントを持っている必要があります。一方、参加者は登録不要かつ無料で参加が可能です。
※詳細は、公式サイトをご覧ください。
Microsoft Teams
マイクロソフト社が提供する企業向けのチャットツールです。ビデオツールとしても活用が可能で、無料版で100人まで接続が可能ですので、参加人数に応じて選択されると良いでしょう。
※詳細は、公式サイトをご覧ください。
Web説明会のメリット

Web説明会に対する学生の意見をふまえたうえで、開催するメリットやデメリットについて見ていきましょう。
母集団形成への貢献
Web説明会の最大のメリットは、参加者のハードルを下げることです。そのため、地方在住や海外留学中といったオンサイトでの参加が難しい学生の参加ハードルを下げ、これまでアプローチできなかった学生層を取り込むことができます。
採用活動における母集団形成は最終的な入社数にまで影響を与える要素ですので、この母集団の数を増やすことは大きなメリットだといえるでしょう。
採用コストを抑えることができる
オンサイトでの説明会は、1回の開催に会場手配、設営、受付、片付けといった手間やコストが発生します。地方での開催実施となれば、さらに、出張交通費や移動時間なども発生してしまいます。
また、会場設営・撤去のためのスタッフも必要となる場合もあるでしょう。スタッフの人件費も馬鹿にはなりません。
一方、Web説明会はツールさえあれば、どこでも開催が可能です。担当する社員もリモートワークしている自宅から参加することができるため、交通費や移動時間の削減にも寄与します。また、就活生にとっても、交通費や移動時間がかからないため、気軽に参加することができます。
参加者との対話も実現できる
開催形式によりますが、やり方によっては少人数のグループに分けてディスカッションしてもらったり、そのなかに社員が入って一緒にコミュニケーションすることも可能です。リアルだと会場内の移動も大変ですが、オンラインであればボタン1つで移動が可能ですので、コミュニケーション効率を高めることができるでしょう。
Web説明会のデメリット

学生からの質問が得られにくい
Web説明会は、気軽に参加できる反面、途中退出されてしまうことも発生しやすいと言えます。画面越しのため、学生とコミュニケーションがとり辛いと感じる場合もあるでしょう。
「質問はありますか?」と投げかけても、学生から反応が返ってこず、担当者は学生への声掛けに悩まれる方も少なくありません。ここについては、企業側として工夫の余地があるといえるでしょう。
リアルを伝えることが難しい
当然ながらオンラインとなると、社員の雰囲気を知ってもらったり、自社サービスを体感してもらったり……といった事柄は難しくなります。そのため、一方的な説明になりがちで、企業理解の深度を懸念される人は少なくありません。
途中退室されることがある
Web説明会は手軽に参加しやすい反面、ボタン1つで途中退室できます。学生の興味関心がある情報を提供できなければ、参加者は「この企業は自分に合わないかもしれない」「つまらない」といった理由で途中退室されてしまう可能性があります。
Web説明会の実施手順

Web説明会を成功させるためには、万全な準備が不可欠です。準備を怠ると、当日に問題やトラブルが発生して進行が滞る恐れがあります。以下で解説する実施手順を参考に、Web説明会の準備を進めましょう。
環境を整備する
Web説明会のライブ配信や動画撮影をスムーズに行うためには、環境の整備が欠かせません。とくに初めてライブ配信を行う場合は、次のようなトラブルが起こりやすいので注意しましょう。
- 接続不良の問い合わせがくる
- 照明が暗く、見えづらい
- 資料の投影ができないなど
資料を作成する
Web説明会で画面共有する資料としてスライド作成が必要です。1スライドあたり40秒で説明できる簡潔な内容にまとめるのが理想的でしょう。事前に紙の資料を配布する場合は、読み応えのある内容にするのも1つの方法です。
日程や服装、必要な物など学生に周知する
Web説明会の参加方法、服装、必要な物などを周知することで、学生は参加前に感じる不安や疑問を解消したうえで参加してもらえます。
分からないことがあると、学生が参加をためらってしまう可能性もあります。できるだけ詳しい情報を伝えましょう。
Web説明会の録画配信を視聴してもらうためのポイント

Web説明会の動画を学生に視聴してもらうためには、録画配信のメリット・デメリット、コンテンツ作成のポイントを押さえておく必要があります。ここでは、録画配信のメリット・デメリットや作成時のポイントを解説します。
録画配信のメリット・デメリット
録画配信は、Web説明会に参加できなかった学生をはじめとする幅広い層に自社の情報を提供できます。録画配信のメリット・デメリットを把握したうえで、自社を効果的にアピールするためのコンテンツ作成に活かしましょう。
録画配信のメリット
- 再生・一時停止などの操作が簡単でメモが取りやすい
- 聞き逃した部分のみ再生できる
- 視聴者の都合に合わせて見てもらえる
- 繰り返し視聴してもらえる
- Web説明会の参加者以外の学生にも情報を発信できるなど
録画配信のデメリット
- リアルタイムでの質疑応答ができない
- 緊張感がなく、会社説明会に参加している実感を得にくい
- 視聴者の集中力が長続きしにくい
- 社風や実際に働く社員の人柄、職場の雰囲気が伝わりにくい、など
録画配信のコンテンツ作成のポイント
録画配信を学生に視聴してもらうためには、前述したデメリットを考慮したコンテンツを作成する必要があります。以下で録画配信のコンテンツを作成する際のポイントを解説します。
▼関連資料
【お役立ち資料】採用動画は複数用意する時代!自社制作できる採用動画
学生からの質問に答えるプログラムを組み込む
学生から尋ねられる質問を想定してQ&Aの内容をコンテンツに作成しましょう。Q&Aをプログラムに組み込むことで、録画配信を視聴した学生の不安や疑問を解消できるコンテンツを作成できます。またリアルタイムでの質疑応答ができない問題点を解決できるため、学生が不安や疑問を抱えたまま視聴することを避けられます。
コンテンツをセグメント分けする
希望職種や学生の専攻をセグメントに分けてコンテンツを作成しましょう。学生に合ったコンテンツを提供すると、Web説明会の持っている「緊張感がなく、会社説明会に参加している実感を得にくい」という問題点の解消につながります。セグメント分けの例は次のとおりです。
- 希望職種(営業・広報・総務など)
- 学生の専攻(理系・文系など)
最適な時間配分(30分〜1時間程度)にする
時間配分に配慮したコンテンツを作成することで、「視聴者の集中力が長続きしにくい」というデメリットを解消できます。動画が長すぎると集中力が続かず、途中退室する学生が増える可能性があるので注意しましょう。
座談会形式で「社風」や「雰囲気」を感じてもらう
座談会形式とは、社員同士がコミュニケーションを取りながら進めるスタイルです。社員同士のやり取りを学生に見せることで、自社の社風や社員の人柄、雰囲気を感じてもらえます。座談会形式の録画配信にすると、「社風や実際に働く社員の人柄、職場の雰囲気が伝わりにくい」というデメリットの解消につながります。
次のステップにつながる仕組みを作る
録画配信は、学生の次の行動を促す仕組みを作ることが大切です。録画配信を視聴しただけで終わってしまうと、学生に取ってほしい行動を促すことができません。
コンテンツ作成時は、「視聴した学生のみ参加可能な説明会へ招待します」「最後まで視聴した学生は1次選考を受けずに面接へ進めます」などのオプションを設けて、参加者を集める仕組みを作りましょう。
Web説明会を成功させるための3つのポイント

最後に、Web説明会を成功させるための3つのポイントをご説明いたします。
魅力あるコンテンツや進行を意識する
オンライン/オフライン問わず、まず重要となるのが魅力あるコンテンツ作りです。最近の学生は動画にも慣れており、企業研究をYouTube等で行う時代です。目の肥えた学生が飽きない内容を意識しましょう。
最も重要なポイントは、学生が知りたいコンテンツとは何かを意識することです。対面でのコミュニケーションが難しくなったからこそ、以下のような要素が伝わるコンテンツを意識してみてください。
・同業界・同規模の企業と比較した際の自社の強み ┗一例)市場の安定性、独自技術、過去5年間の経営状況、売上高、従業員数…等 ・事業の魅力 ┗一例)ニッチ領域だけど実は生活に身近な製品、取引先が大手…等 ・社員や会社の雰囲気 ┗一例)熱く仕事について語れる社員の登壇、社員に対する上層部の想い…等 ・独自の福利厚生 ┗一例)バースデー休暇、地方からフルリモート可、資格取得支援制度…等 |
また、プレゼンテーターの話し方や立ち居振る舞いも重要な要素の一つです。ノンバーバルのコミュニケーションが伝わりづらいため、いつも以上に身振り・手振りを意識したり、説明する内容によって担当を変更するなどして、飽きさせないよう工夫しましょう。
これらをふまえた上で、ライブ配信型説明会の場合はインタラクティブなやり取りを意識することが重要となります。
ライブ配信型と録画配信型の使い分け
ライブ配信型と録画配信型を用途に応じて使い分けることも重要な要素の一つです。
例えば、ライブ配信型はリアルタイムで就活生とコミュニケーションを取れることがメリットです。チャット機能を必ず利用し、人事担当者が説明している最中でもどんどん質問が出てくるように、企業側から質問やクイズ等を交えると良いでしょう。オフラインでの説明会とは異なり、チャットという気軽な手段を用いることで参加者からも質問が集まりやすくなります。
また、リアルの場ではなかなか参加できないような社員に登場してもらうことも可能ですので、海外駐在中の社員や海外グループ会社の役員に参加してもらう先輩座談会などを企画することで、リアルの場以上の意向醸成も可能でしょう。
一方、録画配信型説明会は、一方的な説明になりがちです。伝えたい内容をわかりやすく端的にまとめて、長くても30分程度で終了するなど、構成に工夫を凝らしましょう。
自社での制作が難しいという場合は、動画制作会社に依頼すれば質の高い動画を制作することも可能です。また、自社で行いたいという場合でも、資料・台本・機材を準備し、動画編集ソフトを上手く活用できればコストをかけずに比較的質の高い動画制作も可能でしょう。
録画配信型説明会は、多くの学生に視聴してもらいエントリーの母集団形成に利用することが多いため、業界の理解が進んでいない就活生にもわかりやすい内容にすることが重要です。
面接などの次のステップへの導線設計
通常の会社説明会では、終了後にそのまま面接や筆記試験を実施したり、アンケートを回収したりして就活生の個人情報や選考参加希望を確認し、次のステップへ誘導します。しかしながら、オンライン説明会では、終了後にWebアンケートを実施したり、応募フォームへ誘導したりするなどを行わなければ簡単に離脱されてしまいます。
気軽に参加できるからこそ、次の導線設計は非常に重要になります。
特に録画配信型説明会では、情報を全て閲覧したかどうかの確認が難しいため、事後アンケートの内容に”動画内で出てきた情報、且つ企業として一番理解してもらいたい内容”を確認する設問を用意するなどの工夫が必要です。理解してもらえていることを確認しながら次のステップに進んでもらうことで、選考途中で就活生が理解不足によって離脱するのを防ぐことができます。
▼関連記事
改めて、最後にライブ配信型と録画配信型におけるオンライン説明会を成功させるポイントを振り返っておきましょう。
▼ライブ配信型を成功させるポイント
・説明会前のアイスブレイクでは、チャット機能を試しに利用してもらうなど質問が出やすい状況を作る ・「zoom」などの場合投票機能があるので、「今日の説明会で何を知りたいか」といった質問を投げかける ・プレゼンテーターは、身振りや手振りをいつも以上に意識し、説明内容によって人を変える工夫をする ・説明会後に、普段なかなか会えない社員(海外常駐社員など)も参加する先輩社員座談会を実施し社員の魅力や仕事の魅力を伝える場を設ける |
一方で、録画配信型説明会の場合は、通常の会社説明会の録画配信を行う場合と、別で撮影したものを配信する場合がありますが、いずれの場合でも気軽に視聴できるため、途中離脱されやすい傾向が高まります。
▼録画配信型を成功させるポイント
・30分以下で会社説明の重要なポイントを簡潔にわかりやすく伝える ・30分を超える場合は、学生の仕事観醸成につながる内容や、学び・気づきが得られるコンテンツを盛り込む等の飽きさせない工夫をする ・普段見ることができないような会社のリアルな映像や、社員の普段の様子なども配信して親近感がわくようなコンテンツにする。 ・司会者とは別に登場人物(現場社員・役員)に出演してもらい対話型のコンテンツや、ライブ配信などで実際に就活生から上がった質問に答える形で進行するなどの工夫をする |
まとめ

Web説明会は、母集団形成や採用コストの軽減などのメリットがある一方で、途中退室されるリスクがあります。より効果的な方法で自社が求める人物像に近い学生へ直接アプローチするなら、dodaキャンパスにご相談ください。
▼関連資料
【お役立ち資料】Z世代から支持される「オンライン説明会の作り方」