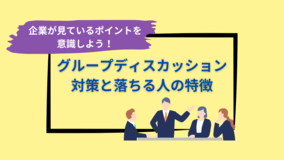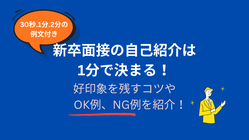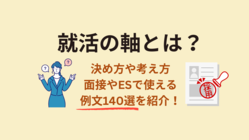就活の選考でよく登場する「グループディスカッション(GD)」。初めて挑戦する方にとっては、何をどう進めればいいのか不安も多いはず。
本記事では、GDで押さえておきたい基本の進め方や、テーマ別の対策ポイントをフレームワークとともに解説。成功のコツを知って、自信を持って臨めるようになりましょう。
目次
GDで使えるフレームワークと思考法
グループディスカッションでは、限られた時間で論点を整理し、説得力のある結論を導く必要があります。そんなときに役立つのがフレームワークや思考法です。
「ロジックツリー」「3C分析」「SWOT分析」などフレームワークの使い方
GDで議論が抽象的になりそうなら、「ロジックツリー」や「3C分析」、「SWOT分析」などを使うと、論点を体系的に整理できます。
- ロジックツリー:問題やテーマを分解していき、要因や論点を細分化する。
- 3C分析:マーケティング系の議題で「顧客」「自社」「競合」を切り口に議論する
- SWOT分析:課題や新規事業のリスクとチャンスを洗い出す
ただし、フレームワークは使い慣れていないと、議論をまとめるのが難しい側面もあります。普段から身近な課題を見つけ出し、使い方を練習しておくのがおすすめです。
例えば、ロジックツリーであれば、アルバイト先の売上減少を想定し、下記のような練習ができるかもしれません。
【テーマ:店舗売上減少の原因を整理する】
- 第一階層: 売上低下の要因を「顧客数の減少」「客単価の低下」に分解する
- 第二階層: 顧客数の減少の要因を「新規顧客の獲得不足」「リピーター減少」に分解する
- 第三階層: 新規顧客の獲得不足の理由を「広告露出の不足」「商品認知度の低さ」に分解する
このように整理していけば、問題の本質や解決すべき具体的なポイントが見えやすくなります。
KJ法やマインドマップなどの使い方
発言が少なくアイデアが枯渇しているときには、KJ法*1やマインドマップ*2などでアイデアを引き出してみましょう。
【テーマ:店舗売上減少の原因を整理する】
- *1:KJ法……多くの意見をグループ分けし、整理するための手法。付箋やカードなどにアイデアやデータを書いて貼りだし、類似するもの同士をまとめていくことで、 問題の本質や新しい視点が発見しやすくなる
- *2:マインドマップとは……テーマやキーワードを中心に書き、枝葉に関連するアイデアや情報を書いて、情報を整理していく手法。 発想を広げたり、本質的な課題を発見する時に役立つ
例えば、下記のような使い方ができます。
- 新商品を考える時のアイデアが出ない→KJ法で多方面からアイデアを可視化
- テーマが漠然としていて整理できない→マインドマップで思考をブレイクダウンする
これらの手法を知っておくと、発言が少ない時でも議論が進みやすくなるでしょう。
GDでは、グループをまとめる「リーダー役」や、時間配分を管理するタイムキーパーなど、さまざまな役割があります。自分が得意な役割がわからない時は、ベネッセ独自の適性検査「GPS」を試してみませんか?リーダーシップや分析力など、 自分では気づかなかったパーソナリティや強みがわかります。
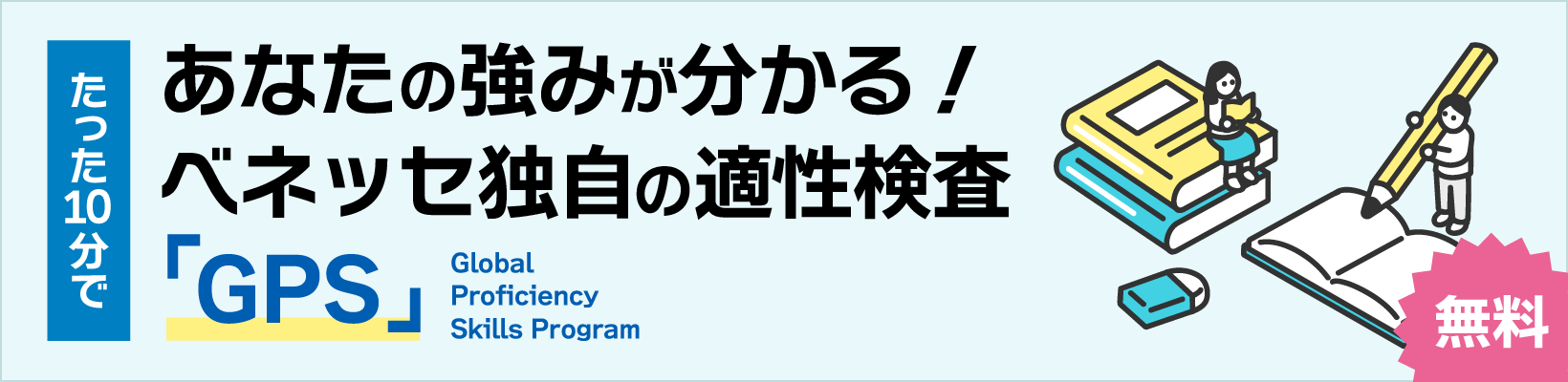
GDの練習で扱うテーマ例
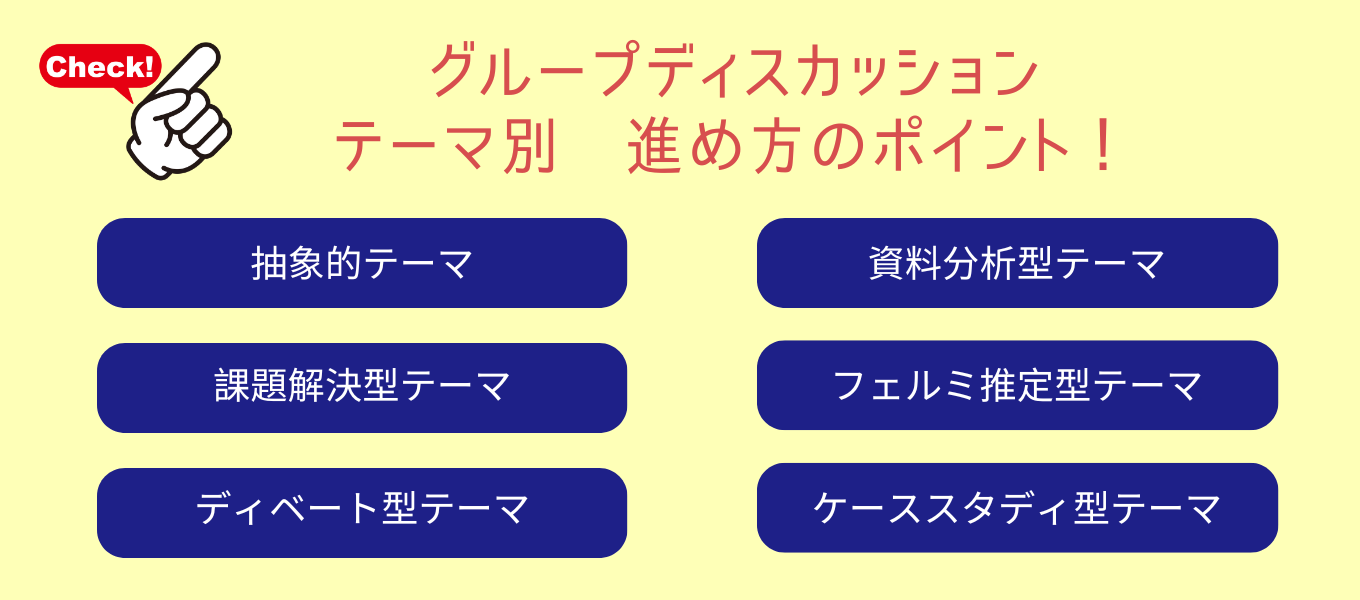
グループディスカッションでは、さまざまなテーマが出されます。
テーマの種類によって議論の難易度や方向性が大きく変わるため、さまざまなパターンを試しておくと本番で対応力がつきます。いくつかの代表的なテーマについて、どのようにディスカッションをすればいいのか、モデルケースを見てみましょう。
【抽象的テーマ】自社オフィスを移転するが最適な移転先は?
このような抽象的なテーマの場合は、メンバーによって価値観が違うため、意見もバラバラになりがちです。「では、順番に意見を言っていきましょう」といった進め方をすると、結論が一向にまとまらず、議論が破綻する恐れがあります。
抽象的なテーマの場合は、はじめに「議論の前提条件」を設定しましょう。上記の例なら、「オフィスを移転する目的はそもそも何なのか?」という前提をはっきりさせていきます。
【抽象的テーマについてディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・前提条件を決める:10分 ・意見を出し合う:8分 ・意見をまとめて結論に持っていく:10分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・テーマの前提条件を決める(正解はない) ・前提条件をもとに議論を進める |
オフィスの移転を必要とするのは、「業務拡大」「交通アクセスの向上」など、様々な目的があるはずです。メンバー全員で共通の認識を持つことから始めないと、抽象的なテーマには対応できません。
仮に、「交通アクセスの向上」がオフィス移転の前提条件だったとしましょう。この前提条件があれば、議論を「交通アクセスが悪いならどこに移転するのが最適か?」という方向に持っていくと結論を出しやすくなります。
【課題解決型テーマ】新商品販売のマーケティング戦略は?
課題に対する具体的な提案や、解決策を導き出すテーマについても見てみましょう。このテーマは、就活のグループディスカッションでも頻繁に出されるテーマです。
課題解決型テーマについて議論する時は、「根拠がある答え」を導き出す事です。
【課題解決型テーマについてディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・仮説を出す:5分 ・仮説が間違っていないか根拠を考える:13分 ・意見をまとめて結論に持っていく:10分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・仮説を多く出す ・仮説から根拠立てて結論を導き出す |
納得感のあるアイデアとは、具体的な根拠や数値が伴ったアイデアのことです。アイデアを出すだけなら、それほど難しくはないでしょう。企業が評価するのは、「根拠があり、納得感あるアイデアを出そうとする過程」です。
新商品販売のマーケティング戦略について議論する場合は、下記のように推論してみましょう。
- どのようにすれば売れるか?
- 他社の成功事例はないか?
- どんな訴求が消費者に響くのか?それはなぜか?
本質的な部分について意見を出し合うのがポイントです。
【ディベート型テーマ】テレワークは生産性向上に効果的か?
ディベート型のグループディスカッションでは、あるテーマに対して賛成派と反対派に分かれ、それぞれの立場を論理的に主張する力が求められます。
ポイントは、立場ごとの根拠を明確にし、説得力のある主張をする事です。
【ディベート型テーマをディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・論拠や主張の準備:10分 ・ディスカッション:18分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・賛成派と反対派で、それぞれ意見を決めておく ・説明根拠がある意見を採用しつつ、もう一方の意見も取り入れた結論を導き出す |
ディベート型テーマの場合は、「実際には何が正解か?」といったことは深く考えずに、根拠立てて説明ができる意見を採用していくと良いでしょう。
テレワークに関するテーマなら、「政府の調査によると、テレワーク導入後に生産性が向上した企業は50%に上るというデータがあります」など、数値的な根拠があれば説得力が増します。
議論をスムーズに進めるために、はじめに「生産性向上の基準」を決めておくことも重要です。具体的には、「労働時間の削減=生産性向上」なのか、「売上や成果の向上=生産性向上」なのか、定義を統一しておけばスムーズに議論できるでしょう。
最終的には、両者の意見を踏まえ「企業が取るべき最適な働き方の提案」を導き出すと、議論の質が高まり、高い評価を受けやすくなります。
【資料分析型テーマ】売上データから見える課題と改善策は?
資料分析型のグループディスカッションでは、与えられた売上データや市場情報をもとに、適切な改善策を導き出す力が求められます。
企業側は、「論理的思考力」「課題発見力」「課題解決力」を見ています。
【資料分析型テーマをディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・資料分析:5分 ・課題の洗い出し:10分 ・対策の検討:13分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・データから、できるだけ多くの問題点を出す ・問題点に共通する本質的課題を考える ・課題解決のための具体策を考える |
資料分析型のテーマでは、売上データや消費者アンケートの結果など、さまざまなデータが提供されます。それらのデータに問題が隠されているため、メンバー全員の違った視点で「なにが問題になっているのか?」を洗い出しましょう。
問題が明らかになったら、その問題を発生させる 「本質課題」を導き出していきます。例えば、「地方での売上が鈍化している」という問題を整理できたのなら、「なぜ地方だけ売上が低いのか?」という本質的な部分を探っていきましょう。もしかすると、地方の営業力が弱いということではなく、「マーケティング調査ができていないこと」や、「ニーズに沿った商品を販売できていない」という点が課題かもしれません。
対策を練る際は、できるだけ現実的な対策を考え、「誰が、いつまでに、なにをやるのか?」などスケジュール感を描きつつ結論を導き出しましょう。
【フェルミ推定型テーマ】日本全国のカフェの年間売上は?
フェルミ推定とは、明確なデータがない状況で、数値を推測する思考力を試す問題です。企業のグループディスカッションでは、論理的思考力や計算のプロセスを組み立てる力が評価されるため、答えが正確かどうかより導き出す過程が重視されます。
【フェルミ推定型テーマをディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・前提の整理:10分 ・計算プロセスの組み立てと検証:10分 ・結論を導き出す:8分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・前提、仮説、計算の順番で考える ・正解はないため、根拠立てて説明できるかに集中する |
フェルミ推定型テーマのポイントは、「前提を設定し、仮説を立て、段階的に計算すること」です。例えば、「日本全国のカフェの年間売上は?」というテーマでは、下記のように推論していきましょう。
- 前提を設定し仮説を立てる:日本全国のカフェの店舗数を推測する。コンビニの店舗数(約55,000店)と比較し、カフェはその半分程度と仮定 → 約25,000店舗
- 店舗あたりの売上を推測する:1日あたりの客数を100人、平均単価を500円と仮定 → 1日あたりの売上は100人×500円=50,000円
- 年間売上を計算する:1店舗の年間営業日は350日 → 1店舗あたりの年間売上は50,000円×350日=1,750万円。全国のカフェの総売上は1,750万円×25,000店舗=約4.3兆円
フェルミ推定型の議論では、「回答の正確さ」より、「議論の流れが明確で論理的かどうか?」が重視されます。ただし、計算過程が複雑になりすぎないように、難しく考えないことも上手く進めるコツです。シンプルな仮説を立てて進めると、限られた時間内で結論を導きやすくなります。
【ケーススタディ型テーマ】チームの意識改革の方法は?
ケーススタディ型のグループディスカッションでは、本質的な課題を見つけ、具体的な解決策を見いだせるかが問われます。企業側は、「論理的思考力」「課題解決能力」「リーダーシップ」などを評価しており、就活のGDでは比較的多く出されるテーマといえます。
【ケーススタディ型テーマでディスカッションする場合のポイント】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間配分(所要時間30分と仮定) | ・役割分担:2分 ・問題の洗い出し:5分 ・本質的課題の抽出:10分 ・課題対策を練る:5分 ・結論:8分 |
| ディスカッションを進めるコツ | ・表面上の課題ではなく、本質課題を洗い出す ・主体性を持った回答を心がける |
「チームの意識改革の方法は?」というテーマでは、「〇〇チームの▲▲さんはモチベーションが下がっており業務成績も伸び悩んでいる」といったケースが出されます。ケースを読めば、いくつかの問題は整理できるでしょう。ただし、重要なのは本質的課題を導き出すことです。
例えば、「▲▲さんのモチベーションが下がっている」という問題に対しては、つい「上司がフォローする」「メンバーが励ます」といった対策を考えがちです。しかし、ケースをよく読むと、「人事評価制度に欠点がある」「報酬制度に問題がある」「部署間の連携が悪い」といった、本質的課題が見つかるかもしれません。
本質的課題が見つかれば、あとはスケジュールを決めて、具体的な対策を考えていきましょう。対策を話すときは、「自分ならどうする?」など、主体性を持った話し方をすると好印象です。
自分が「どんな役割で活躍できそうかイメージがつかない」という方は、これまでの経験や価値観を言語化するところから始めてみませんか?dodaキャンパスであれば無料で生成AIが言語化します!
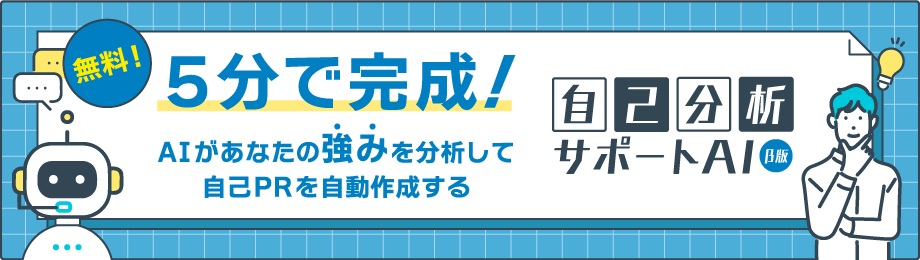
FAQ|GDのよくある不安を解消しよう!
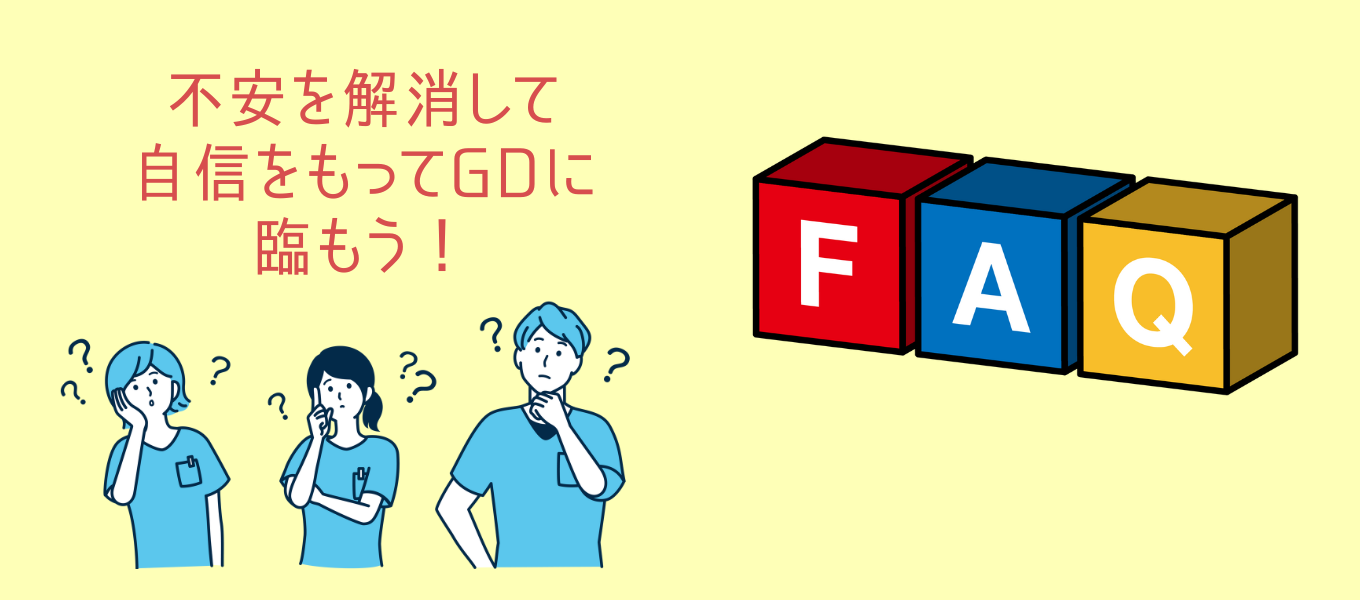
初めてグループディスカッションに参加するとなると、「話がまとまらないのでは?」「緊張して発言できないのでは?」など不安は多いものです。
GDに参加する時にありがちな、よくある不安についても、いくつかアドバイスしていきたいと思います。
話が脱線してまとまらない時の対処法は?
話が脱線してまとまらない時は、一度立ち止まって「ゴールをどこに設定するか」を明確にしましょう。
例えば、「新商品の販売戦略を考える」というテーマでGDをすると、「新商品の開発」や「販売方法の検討」など、さまざまな意見が出てしまうでしょう。まずは議論の最終ゴールを決めてみると、意見を絞りやすくなります。
具体的には、「さまざまな戦略がありますが、今回は販売方法に絞って考えましょう」と誘導すると、結論も出しやすいでしょう。
発言が少なく議論が進まない時はどうする?
誰も発言しない沈黙状態が続くと、議論が先に進みません。そのような状況に陥ったら、「まず、〇〇について順番に意見を出してみませんか?」と提案してみましょう。
自分が先頭を切って発言していけば、きっと話しやすい雰囲気が生まれ、積極的に意見が飛び交うようになるはずです。アイデア出しの際にはKJ法やマインドマップを用いて、「とにかく量を出す」方法を試してみましょう。
自分の役割がない時はどうすれば良い?
リーダーやタイムキーパー、発表者などが他の人に割り当てられ、自分が「何も役割がない」と感じる場合があります。
そんなときは、「書記」として議論をホワイトボードや紙に整理したり、「ファシリテーター」的に意見を引き出す役割を申し出てみましょう。自発的にチームをサポートしようとする姿勢が評価につながります。
自分が発言するタイミングがわからず黙ってしまう場合の対処法は?
「話に割り込むのが苦手」「うまく意見を言えずに沈黙してしまう」という方は、「議論パートになったら、最初に私から意見を出してもいいですか?」と宣言しておくのがおすすめです。リーダーが発言を促してくれない場合は、自分で積極的にアピールしないと埋もれてしまいます。
いきなり発言するのが苦手なら、小さく手を上げてみる方法も試してみましょう。小声で隣にいる人に小声で意見を出しながら、そのタイミングで「ちょっといいですか?」と話しかけてみましょう。スムーズに意見を言えるはずです。
グループにクラッシャーが居る場合の対策は?
「クラッシャー」とは、議論をわざと混乱させたり、自分勝手にリーダーシップを発揮して全てを握り潰そうとするようなメンバーのことです。
対処法としては、クラッシャーが主導権を握りすぎないよう議論全体を制御してみるのが良いでしょう。あえてクラッシャーの意見を一度受け止めつつ、冷静に「他の方の意見も聞いてみましょう」と促すのが効果的です。
感情的に対立するのは避け、全員で進める姿勢を貫くと、きっと良い議論になります。
時間切れで結論を出せないと落ちる?
グループディスカッションでは、最終的に何らかの結論を出すことが求められています。
内容や参加するメンバー次第では、時間内で結論を出せないこともあるでしょう。時間切れで結論を出せないと、「時間管理ができないと思われるのでは?」と感じますが、実はそうではありません。時間がない中で、どのように協力して議論していくか?という過程が見られています。
ただ、やはり時間内に終わったほうが達成感もあり、発表者もアピールできる機会がもらえます。万が一時間ギリギリになった場合は、簡単でもいいので結論をまとめるよう努力しましょう。
与えられたテーマについての知識がない時は?
自分の知識が全くないテーマの場合、知ったかぶりで無理に話すのは避けたほうが良いでしょう。なぜなら、グループディスカッションでは、知識の有無だけで合否が決まることは少ないからです。
たとえ知識がなくても、議論の前提となる仮説を考え結論に導こうとする、その過程が重要視されます。
チームの中でそのテーマについて詳しい人がいたら、知識はその人から共有してもらい、自分は「議論の整理」や「時間管理」といった役割を積極的に担いましょう。
就活について悩むときは
大学3年生になると学業や部活・サークル、アルバイトなどで忙しくなり、就活との両立に悩む方も多いのではないでしょうか。自分に合った企業を見つけ、納得のいく就職活動を進めたいと思っていても、限られた時間の中で何をどう進めれば良いか迷うこともあるはずです。
そんなときは、dodaキャンパスを活用してみてください。dodaキャンパスは、あなたの魅力を知った企業からオファーが届くベネッセの就活サービス。登録しておけば、自分自身では知り得なかった企業からオファーをもらうことができます。
また、自己分析やエントリーシート、志望動機といった気になるトピックスに関するイベントも随時開催していますので、こちらもチェックしてくださいね。
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
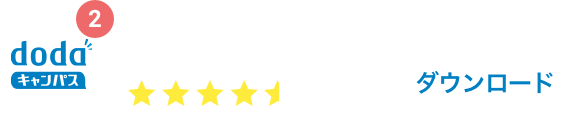

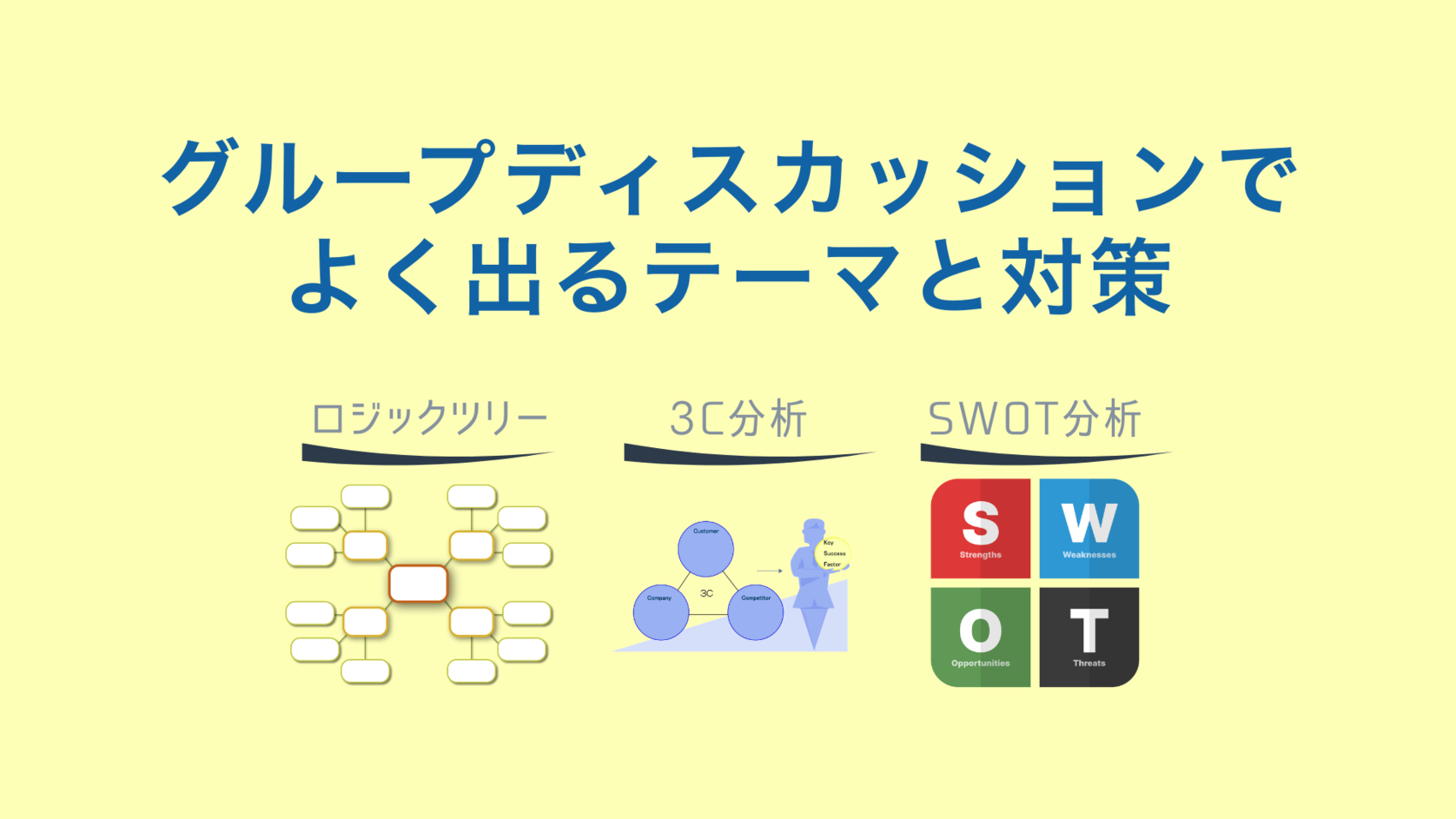

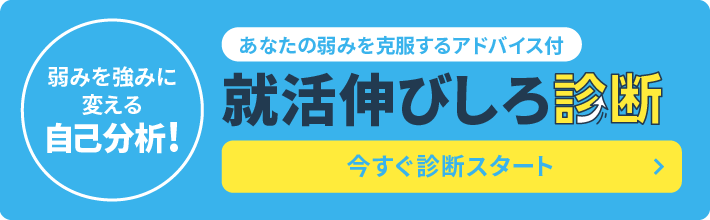
 シェア
シェア