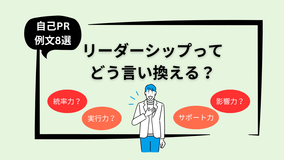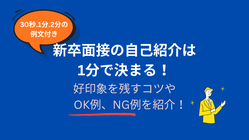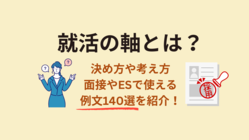ES(エントリーシート)や面接で自己PRをする時は、企業が求める人物像をよく考えながら、具体的なエピソードを交えて話すのがポイントです。
今回は、自己PRの基本的な定義から作り方、そして「アピールポイント別」と「職種別」で、実際の面接で使える例文をご紹介します。
短い自己PRでも好印象を与えるコツや、「自己PRが何も無い」と感じたときの対処法も参考にしながら、採用に一歩近づく面接になるよう準備しましょう。
目次
自己PRの基本的な定義
自己PRは、あなたの「人となり」や「強み」、入社後に貢献できることなどをアピールする貴重な機会です。
はじめに、自己PRの正しい定義と自己紹介との違いについて押さえておきましょう。
自己PRの定義(自己紹介との違い)
自己PRとは、自分の強みや得意分野を伝え、その上でどのように貢献していくのかをアピールすることです。一方、自己紹介は自分の名前や大学名など、基本的な本人情報を伝えることを意味します。自己紹介で自分の強みを語ったり、自己PRの場面で名前や大学名などを言ったりする必要はありません。
以下の表で、自己紹介と自己PRの違いを簡単に比較してみましょう。
| 種類 | 目的 | 伝えるべき内容 |
|---|---|---|
| 自己紹介 | 自分が何者なのかを相手に知ってもらう | 名前・大学名・学部などの基本情報 |
| 自己PR | 自分の特徴や強みをアピールし、どのように貢献できるか示すこと | 強み・具体的なエピソード・成果など |
企業が面接で自己PRを求める理由

企業が面接で自己PRを求めるのには、下記3つの理由があります。
- 応募者の人となりを見るため
- 自社の人材像とマッチしているかを見るため
- 入社後の活躍イメージを測るため
1. 応募者の人となりを見るため
企業は、自己PRに含まれるエピソードや成果から、「どのような性格なのか?」「行動特性にどんな特徴があるのか?」などを見ています。
例えば、「アピールポイントは忍耐力です。学生時代は野球を6年間続け……」という自己PRの場合、企業は「社会の厳しい環境下でも順応できるだろう」と判断するでしょう。
2. 自社の人材像とマッチしているかを見るため
「人材像とのマッチ度」も重要なポイントです。企業は、自社が必要とする能力や考え方を持った人材を探しています。
自己PRで学生の強みや価値観を知ることで、社風や仕事内容とのマッチ度合いを判断しているのです。
3. 入社後の活躍イメージを測るため
入社後にどの部署でどんな仕事を担当し、どのような貢献が期待できるかも企業はイメージしています。
自己PRをする際は、自分の強みや性格を積極的にアピールし、かつ具体的なエピソードを交えましょう。
採用担当者は多くの学生の自己PRを見ています。そのため特に、“あなたらしさ”が伝わるように「私らしさとは?」を追求し、表現として盛り込むよう意識してみましょう。
【採用に一歩近づく!】自己PRの作り方

自己PRを作る時は、やみくもに文章を考えるのではなく、下記4つのステップを踏むと良いでしょう。
- 1.強みを整理する:
過去の経験や他者の評価をたな卸ししましょう。学生時代に打ち込んだ部活や勉強での経験、ボランティア活動などを振り返ると、意外な強みが見つかることもあります。 - 2.エピソードを思い出す:
強みに直結するエピソードを一つか二つに絞り、具体的に語れるようにしておきましょう。 - 3.構成を作って文章をまとめる:
「PREP法*1」や「STAR法*2」などのフレームワークを活用し、読みやすい文章を作りましょう。
「強み→エピソード→入社後の貢献」という流れで構成を組み立てるのがポイントです。 - 4.企業視点に立ち、アレンジする:
企業側がどのような人材を求めているのかを意識しながら、「この強みを生かしてどう貢献するか?」を力強く伝えましょう。
- *1:PREP法
・P (Point) → 結論
・R (Reason) → 理由
・E (Example) → 例
・P (Point) → 再度結論
結論から伝え、具体的な理由などを交えて説得力を持たせる手法です。 - *2:STAR法
・S (Situation) → 状況
・T (Task) → 課題
・A (Action) → 行動
・R (Result) → 結果
具体的なエピソードを通じて、自分の状況などをわかりやすく伝える手法です。
エントリーシート(ES)用と面接用|両方の自己PRを用意しておく
エントリーシート(以下、ES)用と面接用では、アピールの仕方やボリュームが異なるため、両方の自己PRを準備しておくのがおすすめです。
ESは文字情報だけで評価されるため、短い文字数でもインパクトを出す言葉選びや構成力が必要です。一方で、面接では声のトーンや表情、ジェスチャーも加わるため、ストーリー性を持たせることが求められるでしょう。
ESに書ける文字数や面接で与えられる時間も違うため、それぞれのシチュエーションを想像しながら、内容や表現を2パターン用意しておくのがおすすめです。
「自分の強みがうまく言語化できない」と悩んでいる方は、AIに頼ってみるのもオススメ!あなたの経験や考えをもとに、人事担当者に刺さる表現にブラッシュアップできます。
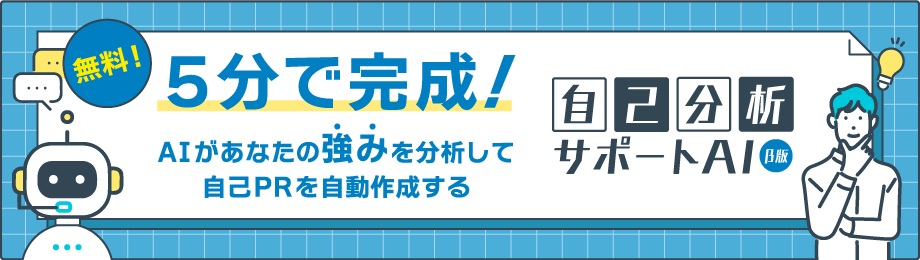
短い自己PRでも面接官に刺さる!好印象を残す3つのポイント

面接では、「自己PRを短くまとめてください」と言われることがあったり、グループ面接で「1分間で自己PRを」と指示されたりすることがあります。
そんな時に「何を話せばいいのだろう?」と慌てないためにも、短い自己PRでも面接官に刺さる、まとめ方や伝え方のコツをご紹介します。
他人にはない強みを積極的にアピールする
多くの学生は「コミュニケーション能力」や「積極性」など、似通った強みをアピールしがちです。
面接官に刺さる自己PRをするには、「自分ならではの強み」は何かを突き詰めて考え、積極的にアピールすることが大切です。
オンリーワンの強みを見つけるには、過去の成果や周囲からの評価を振り返り、自分が一番輝いた瞬間を探してみましょう。
具体例やエピソードを交える
「リーダーシップがあります」や「コミュニケーション能力が高いです」といった抽象的な言葉だけでは、説得力に欠けた自己PRになってしまいます。
「どのような場面で」「どんな問題に直面し」「どんな成果を挙げたのか」といった具体的なエピソードを伝えることで、より強く自分らしさをアピールできるでしょう。
企業が求める人材像を理解した上で答える
自己PRでは、面接官が「うちの企業で活躍してくれそうだ」と感じるかどうかがポイントとなります。
そのため、企業の求める人材像や必要なスキルを事前にリサーチし、「自分の強みを生かして、どう貢献するか?」を関連づけてアピールすると良いでしょう。
また、アピールの際は他の学生に埋もれないよう自分ならではのエピソードを探し、盛り込むとグッと注目度がアップします。

採用担当者に刺さる!自己PRの例文1.「アピールポイント別」

「自己PR」といっても、人によって強みはさまざまです。
今回は、「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」「問題解決力」「継続力」「協調性」の5つを例に、面接で使える自己PRの例文をご紹介します。
自分の強みと照らし合わせながら、文章構成やエピソードの見せ方を学んでみましょう。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力をアピールする際は、単に話し上手というだけでなく、相手の意図をくみ取り、円滑に物事を進める力をしっかり伝えましょう。
例文
私の強みは、多様な意見をまとめるコミュニケーション能力です。ゼミでチームが対立した際、このままでは研究目標が達成できないと感じ、自分が主体的に調整役になろうと思いました。各メンバーの意見や希望をヒアリングし、共通の目標を再設定することでスムーズな話し合いを実現した結果、ゼミ全体の成果に貢献できた経験があります。
入社後に、プロジェクトチームで大きな目標を追いかける時でも、持ち前のコミュニケーション能力を生かしてチームを引っ張っていける存在になりたいです。
リーダーシップ
自ら主体的に取り組み、目標達成に向けて周りを巻き込む能力に自信があるなら、リーダーシップを自己PRの中に入れてみましょう。
例文
私の強みは、一人ひとりの特性を活かせるように、チームを牽引できるリーダーシップ力です。大学のサークル活動で、チームを率いて新イベントを企画する際、メンバーが得意なスキルを活かせるポジションを割り当てました。
これは、役割分担が不明確で、全員の能力を十分に活かしきれなかった経験から、個々の強みを最大限に発揮できる環境を作りたいと考えたからです。その結果、全員がモチベーション高く取り組むことができ、イベント成功に大きく貢献できたと考えています。
入社後は、私のリーダーシップ力を生かし、将来は管理職を目指して事業に貢献していきたいです。
問題解決力
問題解決力とは、問題の本質を見極め、適切な対応策を考え実行できる力を指します。社会人になったら、さまざまな問題に向き合う機会が増えます。入社後の活躍イメージも想像しながら、しっかり強みをアピールしていきましょう。
例文
私の強みは問題解決力です。アルバイト先の売上が伸び悩んだ際、このままでは店舗の成長が停滞してしまうと感じ、何か改善できることはないかと考えました。
そこで、原因を分析するために顧客の声を集め、商品の陳列や接客方法の改善案を提案したところ、リピーターが増え、売上が前年同月比10%上がった経験があります。入社後は、さらに問題解決能力を磨き、事業の成長に寄与していきたいです。
継続力
困難に直面しても、粘り強く続けられる性格なら「継続力」を自己PRに入れてみましょう。
例文
私は継続力に自信があります。高校時代から「将来はグローバルな環境で活躍したい」と考えており、英語力を高める必要があると感じました。そこで、毎日2時間の英語学習を3年間欠かさず続けた結果、TOEICのスコアを300点台から800点台にまで伸ばしました。
この粘り強さは、業務の習得や長期的なプロジェクトにおいても大いに活かせると考えています。
協調性
協調性は、集団の中でうまく連携を取りながら、周囲と協力して目標を達成する能力です。
さまざまな個性や背景を持つメンバーと協力しながら仕事を進めるイメージを持ち、自分の強みを伝えると良いでしょう。
例文
私の強みは高い協調性です。大学祭の実行委員会では、メンバー同士の連絡が滞り、チーム全体の作業効率が低下していました。この課題を解決するため、スケジュール管理や情報共有の仕組みを導入した結果、トラブルが減少し、全員が役割を果たしやすい環境が作れた経験があります。
入社後は、さまざまな背景や個性を持つ方と協力する場面が増えると思いますが、この経験を活かし、チームでの成果を最大化できるよう取り組んでいきます。
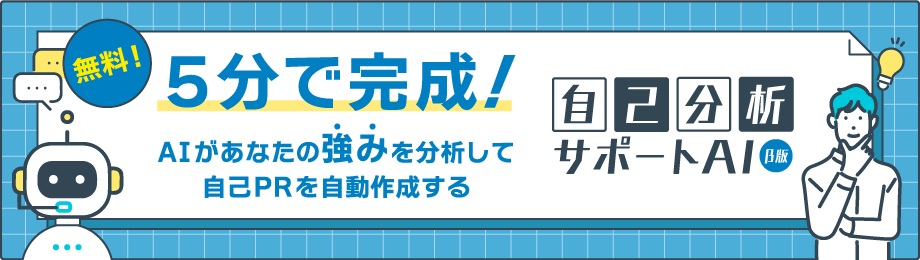
採用担当者に刺さる!自己PRの例文2.「職種別」

面接では、志望する職種に合わせ、自己PRの内容をアレンジしなければならない場面もあります。例えば、「コミュニケーション能力」を自己PRに含める場合、営業職とエンジニア職では、強調すべき点も異なります。
「総合職」「営業職」「エンジニア職」「企画職」「事務職」など、代表的な職種別で使える例文もご紹介しますので、ぜひ説得力ある自己PRを作ってみましょう。
総合職
総合職は、さまざまな部署を経験する可能性があるため、「柔軟性」や「協調性」を自己PRに入れると良いでしょう。
例文
私の強みは、多角的に物事を捉えられる柔軟性です。大学では、サークル間の交流が少なく、個々の活動が限定的であることに課題を感じていました。
そこで、5つのサークルを巻き込み、互いの特色を活かした独自のイベントを企画しました。それぞれの意見を尊重し、異なるアイデアを生かした企画をまとめた結果、多くの来場者を呼び込むことができ、イベントが大成功に終わった経験があります。
入社後は、異なる部署や背景を持つ方々と柔軟に協力し、この経験を活かして御社の事業成長に貢献したいと考えています。
営業職
営業職ではコミュニケーション能力やネゴシエーションスキル、目標達成意識が特に重要視されます。困難な場面を乗り越えたエピソードを含められるなら、より説得力が増すでしょう。
例文
私の強みは、相手と粘り強く交渉できるネゴシエーションスキルです。大学で募金活動を行った際、寄付が思うように集まらず、このままでは活動の目的を果たせないという危機感を抱きました。
そこで、単に募金をお願いするだけでなく、寄付をして下さる方々と丁寧に対話を重ねた結果、活動への共感が広がり目標金額を大幅に上回る成果が出せました。
営業職でも、お客様のニーズを深く理解するために根気強く対話を重ね、信頼関係を構築することで、最適な提案を行いたいと考えています。
エンジニア職
エンジニア職では技術力だけでなく、論理的思考力や問題解決力、チーム単位で目標を達成させる協調性が求められます。
例文
私の強みは、問題解決力とチームワークです。プログラミングの勉強会を立ち上げた際、初心者同士でミスが多発し、スムーズに学習が進まない状況に課題を感じました。
このままではチーム全体の成長が遅れると考え、ミスの改善策をまとめた独自のマニュアルを作成した結果、チーム全体のスキルが向上し、最終的にはアプリ開発コンテストで入賞を果たすことができました。
入社後は、技術力をさらに高めるだけでなく、チームメンバーの方々と積極的に意見を交わしながら、共に大きな目標を達成したいと考えています。
企画職
企画職では、新しいアイデアを生み出し、具体的な形にするクリエイティブさと実行力が求められます。入社後の活躍をイメージしてもらえるようなエピソードがあると、自分の強みをより伝えやすくなるでしょう。
例文
私の強みは、発想力と実行力です。ゼミで地域活性化をテーマにした課題に取り組んだ際、地域特産の野菜が十分に活用されておらず、地域経済への貢献に課題があると感じました。
そこで、地域の野菜を使った新商品の開発を提案しました。独創的なデザインを考えるだけでなく、コスト面や実現可能性も考慮しながら企画を進めた結果、プロジェクトの成果が評価され、学内のビジネスコンテストで最優秀賞を獲得できた経験があります。
入社後は、これまでの経験を活かし、世の中に新しい価値を提供できるサービスや商品を企画し、事業の発展や地域社会の利便性向上に貢献していきたいと考えています。
事務職
事務職は、正確性や効率性・サポート力などが重視される職種です。アルバイトやゼミの経験を思い起こし、ミスなく処理できたエピソードがあるなら、具体的に伝えてみましょう。
例文
私の強みは、正確かつ効率的にタスクを進められる能力です。大学の研究室でデータ入力や書類整理を任された際、作業時間が多く負担になっていることに課題を感じました。
このままでは研究そのものに十分な時間を割けないと考え、効率化を目指してエクセルでマクロを組み、作業時間を半分に短縮しました。その結果作業漏れをゼロに抑えることができ、研究室運営に大きく貢献できた経験があります。
事務職では、正確性に加え、他部署をサポートする力や効率的な業務遂行能力が求められると考えています。持ち前の几帳面さを生かし、さらなる効率化ができるよう工夫を重ねながら貢献していきたいです。
自己PRが何も無い時の対処法

「自己PRに含められるようなエピソードが無い」「他人と比較して、何も取り柄がない」など悩む方も多いでしょう。
「アピールできることがない」と思っていても、フレームワークやAIツールを使えば、隠れた魅力を発見できるかもしれません。
自己PRで話せる内容が見つからない時に役立つ、対処法を2つご紹介します。
フレームワークを活用する
自己PRを見つける際におすすめなのが、「STAR法」と呼ばれるフレームワークです。
以下の手順で整理してみましょう。
- Situation(状況):どんな場面だったか(アルバイト、ゼミ、サークルなど)
- Task(課題):何を求められていたか(売上向上、イベント運営、チームまとめなど)
- Action(行動):具体的にどんな方法で対応したか(コミュニケーションの手法、ツール導入など)
- Result(結果):どのような成果や評価を得られたか(売上○%増、コンテスト入賞など)
経験を体系的に振り返ることで、思わぬ強みやアピールポイントが見つかることがあります。
AIや診断ツールを活用する
自己PRを自力でまとめきれない時は、AI診断ツールを利用してみるのも良いでしょう。AIに自分の経験や得意なことを入力すると、自己PR文の素案を提供してくれます。
ただし、AIで作った文章を、そのまま自己PR文として使うのは望ましくありません。AIで作られた文書をもとに、自分なりのエピソードや言い回しを加筆修正し、オリジナルの文章を作りましょう。
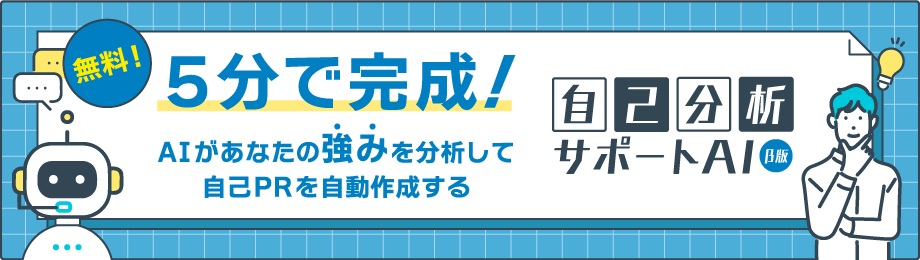
新卒面接での自己PR|よくある質問
面接の本番では、自己PRに関して予想外の指示や質問をされることも珍しくありません。
急に「自己PRを短めで1分以内でお願いします」と言われることもあるでしょう。最後に、新卒面接の自己PRでよくある質問についてもお答えしていきます。
「短い自己PRをお願いします」と言われた時の例文は?
面接官から短めの自己PRを求められた場合は、結論を先に述べて端的にエピソードを伝えましょう。想定外の指示に備え、持ち時間別で2〜3パターンを作っておくのが理想です。
例文
私の強みは、周囲の意見をまとめるコミュニケーション力です。大学のゼミで意見が対立する場面でも、全員の考えを整理して新しい提案につなげ、ゼミ全体の成果向上に貢献できました。入社後も多様性を理解しつつ、どのような人とでも協調性高く業務ができる自信があります。
ポイントは、「強み→具体例→成果」の順に短くまとめることです。時間があまり取れない場面でも、要点を伝えることで好印象を与えられます。
自己PRできるものが何も無い時はどうすればよいですか?
自己PRが思いつかないと感じる場合は、まず小さな成功体験や周囲からの評価を洗い出してみましょう。
些細な経験でも、「人に喜ばれた」「困難を乗り越えた」といったエピソードがあるはずです。フレームワークやAIツールも活用して、自分の経験を整理し、アピールにつなげましょう。
採用されやすい自己PRの方法は?
採用されやすい自己PRを作るには、以下の3点を押さえましょう。
- 企業視点を意識する:応募先の企業が求める人物像に合った強みをアピールする。
- 具体的なエピソードを含める:成果や対応した課題を明確にし、説得力を高める。
- 簡潔かつ論理的に話す:結論から述べたうえで、エピソード→結果→貢献ポイントの流れを意識する。
自己PRは自信を持って強みを伝えよう!
自己PRを話す時は、あなたが大事にしてきたことやコツコツ積み上げたことをしっかり言語化し、企業にどう貢献できるかを示しましょう。
エピソードと強みを結びつけて、採用担当者がイメージしやすいように表現するのがポイントです。
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
関連記事
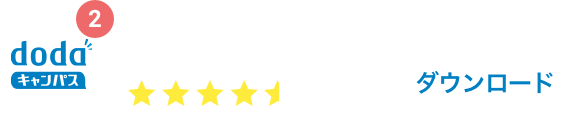



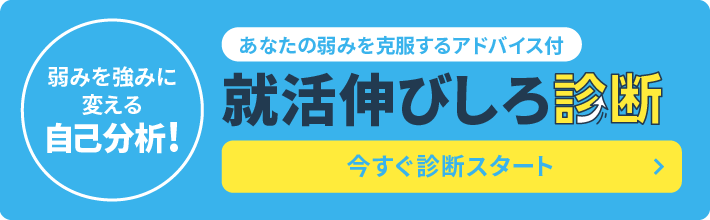
 シェア
シェア