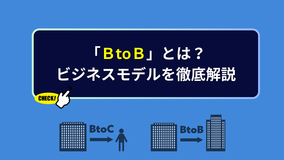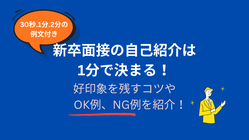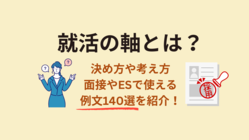「初任給」とは、文字通り「初めて任せられた仕事に対する給与」のことです。企業によっては、企業の募集要項に掲載されている以外の「諸手当」を含めた額となります。
「志望業界(企業)の水準は?」 「平均額はいくらくらい?」 「税金はどのくらい引かれるの?」といった疑問や興味を持つ方もいるのではないでしょうか?
この記事では、これらについて詳しく解説します。入社前に、初任給に関する疑問を解決しておきましょう!
目次
大卒と院卒の初任給平均額の推移は?年収はいくらになる?

厚生労働省の最新の初任給調査「令和5年賃金構造基本統計調査結果」における「新規学卒者の学歴別にみた賃金」によると、大学卒(男女計)の初任給は23万7,300円、大学院卒は27万6,000円でした。
令和2年(2020年)以降、賃金構造基本統計調査の初任給に通勤手当を含めるようになったなど調査定義が変更されたため、以前の調査とは単純に比較はできませんが、過去5年間で初任給は増加傾向にあります。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、1カ月あたりの通勤手当の平均は1万1,700円であり、その結果を踏まえても、過去5年間で大卒・院卒いずれの初任給も1万円近く上がっていることがわかります。
初任給はいつ支払われる?
初任給の振り込み日は、企業内の就業規則によって異なります。
チェックするときは、「締め日」と「支払い日」に注目して確認してみましょう。 例えば「当月末締め、翌月25日払い」の企業では、4月1日入社の場合、5月25日に初任給が振り込まれます。
その他だと「当月○日締め、当月末払い」や「当月末締め、翌月○日払い」などがあり、タイミングは企業によってさまざまです。
業種・企業規模・地域によって初任給が異なる!?

初任給の平均額は、高卒・大卒・院卒といった学歴だけではなく、業種や企業規模、地域によっても異なります。
厚生労働省のデータを元に確認していきましょう。
業種別の初任給平均額
厚生労働省が令和6年に行った大学卒の産業別初任給についての調査によれば、初任給平均額が最も高かったのは「不動産業、物品賃貸業」で約25万円でした。
また、「鉱業、砕石、砂利採取業」が約24万6,000円で2位、「情報通信業」「公務・その他」が約24万5,000円で同率3位となっています。
一方、産業別で最も初任給平均額が低かったのは「複合サービス事業」で、約21万2,000円でした。また、「農林漁業」の初任給も約21万5,000円と同程度の水準になっています。
企業規模別の初任給平均額
続いて、企業規模別の初任給平均額について見ていきましょう。令和6年に厚生労働省が実施した「新規学校卒業者の求人初任給調査」によると、大学卒の方に関しては、企業規模が大きくなるにつれて初任給平均額も高くなっていくという傾向が読み取れます。
同調査によれば、従業員1,000人以上の大企業における大学卒の初任給平均は約22万3,000円です。一方、従業員300~499人の中企業の場合は約22万円で、大企業に比べると約3,000円少ないことがわかりました。
さらに、29人以下の小企業は約21万5,000円で、中企業より約5,000円、大企業より約8,000円下回るという結果となっています。このデータから、企業規模によって初任給に格差があると考えられるでしょう。
地域別の初任給平均額
地域別の初任給平均額を見ると、都会は高く、地方は低いという傾向が認められます。厚生労働省の令和元年の調査によると、東京都の初任給平均額が約22万500円で1位。2位は千葉県で約21万1,700円です。
一方、宮崎県は18万8,000円、沖縄県は17万5,000円など、地方では低い水準にとどまっており、1位の東京都と47位の沖縄県で約5万円の差があります。
dodaキャンパスでは、25問の質問に答えるだけであなたに合った働き方が分かる『キャリアタイプ診断』をご用意!
5分程度でサクッと分析ができるので、ぜひお試しください。その結果を見た企業から、あなたに合ったオファーを受け取ることができます。
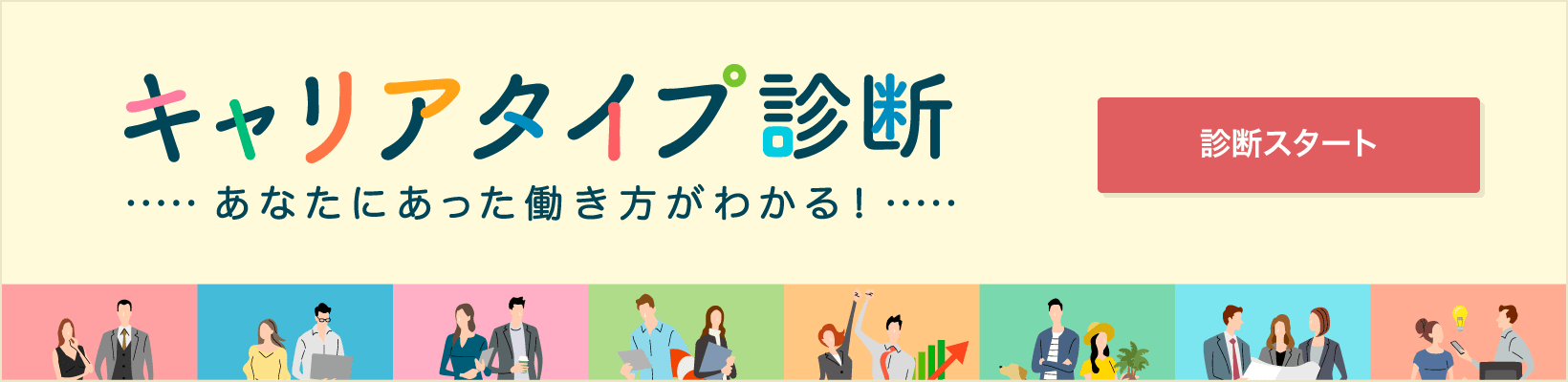
採用告知に掲載されている給与額の内訳は? 諸手当とは?
採用通知書に記載された給与の内訳はどうなっているのでしょうか?給与額は「基本給と諸手当の合計」を指します。
「基本給」とは、固定的に支給されるベースとなる給与です。ここに社員それぞれに与えられる手当が加わり、最終的な給与となります。「時間によるもの」「立場によるもの」といった各種手当について具体例を確認してみましょう。
【時間外手当】
いわゆる「残業手当」です。日本において労働時間は「1日につき8時間以上労働させてはならない(休憩時間は除く)。1週間につき40時間以上労働させてはならない」(労働基準法第32条)と定められており、法定労働時間を超えて労働した場合は時間外手当が発生します。
【深夜・休日勤務手当】
深夜手当は、午後10時から午前5時の間に労働した場合に支払われます。深夜勤務をした労働者には、必ず支払われる必要があります。休日手当は、労働基準法上の「法定休日」に勤務した場合、企業は割増賃金を支払う義務があります。
【役職手当】
一定の役職(管理職やリーダー)に就いた対象者に支給される手当です。
部下の育成や指導、チームの運営や業績向上など、責任の重たい職務に対する対価として支払われます。
【家族手当】
従業員に家族(子供や配偶者といった扶養家族)がいる場合に支給される手当です。少子化対策をはじめ、従業員の生活支援を目的としています。ただし、配偶者の年収が103万円なのか130万円なのかによって定義が異なり、企業によって取り扱いが異なる点は留意しましょう。
【住宅手当】
社員の家賃や住宅ローンの一部を企業が負担する制度です。
企業により支給条件(一律支給/家賃の●●%/住宅ローンの補助)や支給額は大きく異なります。
この他にも「健康手当」「アニバーサリー手当」など、ユニークな福利厚生の一環として独自の手当を設ける企業もみられます。

給料から引かれるものは?額面との違いや手取り額の計算方法を解説!
「額面」は、企業から支給される給与の合計であり、基本給に各種手当が合算されたものです。対して「手取り」は、実際にもらえる給与額を指し、額面のおよそ75〜85%に相当します。給料明細では、差引合計額とも記されているので混同しないよう注意しましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 額面給与(総支給額) | 企業が支払う給与の合計(控除前) |
| 手取り給与 | 税金や社会保険料を差し引いた後の振込額 |
ここでは、額面と手取りの違いについて詳しく解説します。
給与から差し引かれる項目
最終的に私たちが受け取れる初任給は、「額面」の金額から税金や各種社会保険料などが差し引かれた金額です。
| 控除項目 | 内容 | 控除額の目安(額面給与の%) |
|---|---|---|
| 所得税 | 国に納める税金(累進課税) | 約3%〜5% |
| 住民税 | 住んでいる自治体に納める税金 | 約10%(前年の収入に応じる) |
| 健康保険料 | 病院代の一部負担を補助 | 約5%〜10% |
| 厚生年金保険料 | 老後の年金のための保険料 | 約9%(総額18%のうち折半) |
| 雇用保険料 | 失業時の給付に備える保険 | 約0.6%〜0.9% |
では、給与から控除されるものの一例とその内容を実際にみてみましょう。
所得税
給与額に応じてかけられる税金で、給与により控除される額が異なります。所得が増えるごとに税率も増える累進課税制度となり、仮に年収が195〜330万円であれば、税率は10%(控除額は97,500円)です。
住民税
住んでいる都道府県や市区町村に収める税金を指します。
健康保険料
病気や怪我時に、治療費の自己負担額を減らすための保険料です。企業と労働者でそれぞれ半額ずつ支払います。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、毎月の給与とボーナスに対して一定の割合で計算されます。企業と従業員とで折半しており、保険料率は 18.3%です。
額面給与30万円の人であれば、負担額は下記の通りとなります。
30万円 × 9.15% = 27,450円(個人負担分)
⇒企業も同額を負担するので、合計 54,900円を納付
雇用保険料
失業した際に受け取れる「失業保険」を受給するための保険料となります。事業の種類によって保険料率が異なり、一般の事業ならば労働者負担は3/1000です(事業者負担の場合は6/1000)。
その他
企業が独自に運営する仕組みとして寮費や財形貯蓄を行っている場合、該当の金額が引かれます。 例えば、貯蓄制度は給与からの天引きで積み立てることで、計画的に貯蓄を行う仕組みのため、企業によっては初月から引かれることになります。
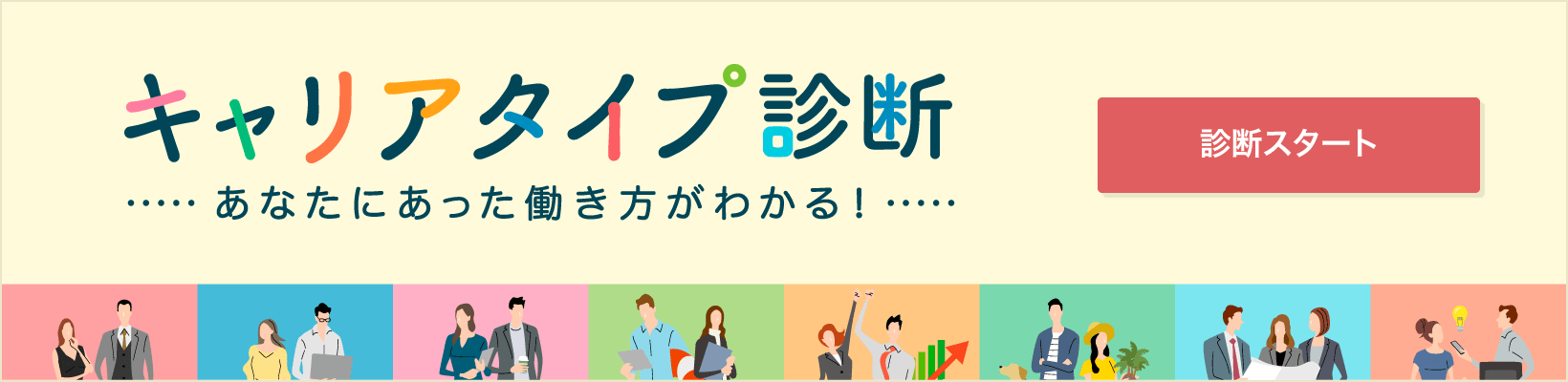
手取り額の計算方法
仮に初任給の額面が20万6,000円だった際の手取り額を計算してみましょう(※未婚、各種任意保険や、ローン、副収入等なし)。先述の通り、初任給で控除されるのは住民税を覗いた「所得税」と「各種社会保険料」です。
初任給の額面と手取り
①雇用保険の計算方法
令和6年度の雇用保険は給与の0.55%(農林水産業、清酒製造、建設などの場合給与の0.6%)で算出します。
20万6,000円×0.0055=1,133円
②所得税の計算方法
1)給与所得控除額を計算
20万6,000円×12ヶ月×0.3+8万円=82万1,600円
※国税庁『No.1410 給与所得控除』より
2)給与所得金額を計算
年収-給与所得排除額
20万6,000円×12ヶ月-82万1,600円=165万400円
3)課税所得金額を計算
所得-所得控除=課税所得金額
165万400円-36万円(社会保険料控除)-48万円(基礎控除)=81万400円
4)基準所得税額を計算
課税所得金額×税率-控除額=基準所得税額
81万400円×0.05-0=4万520円
5)1カ月単位の基準所得税額を計算
4万520円÷12=3,377円
6)手取りを計算
額面-雇用保険料-1カ月単位の基準所得税額
20万6,000円-1,133円-3,377円=20万1,490円(概算)
控除されるのが所得税と雇用保険料のみであるため、初任給は多く感じるかもしれません。しかし5月分からは、厚生年金と社会保険料が差し引かれるようになりますので、手取りはもう少し目減りします。
- 厚生年金の税率:標準報酬18.3%(労働者の負担分は9.15%)
- 健康保険:約10%(労働者の負担分は約5%)※企業によって異なります
おおよそではありますが、20万6,000円の場合は、5月の手取りは以下になります。
5月の額面と手取り
①厚生年金と社会保険料の差し引き額を算出 20万円6,000円×(9.15%+5%)=2万9,149円
②手取りを計算
額面-厚生年金-社会保険料
20万6,000円−2万9,149円=17万6,851円
また2年目の6月からは住民税も差し引かれるようになります。入社1年目から2年目にかけて昇給できていないと、2年目なのに1年目より手取りが少なくなってしまう……という可能性もあるのです。
初任給で生涯年収は決まらない!?初任給だけで企業を選ばないように注意しよう!
待遇や業務内容が同条件で初任給が異なる2つの企業があった場合、初任給を基準に企業を選ぶ人もいるでしょう。しかし、初任給が高いからといって生涯年収も高いとは限りません。昇給頻度やボーナス比率といった要素も生涯年収を決める重要な要素です。
また、公表されている初任給額には、固定残業代などが含まれているということも考慮しなくてはいけません。公表されているのが基本給であれば残業代などは別途で支払われますが、初任給は残業代や各種手当を含めて算出されます。初任給を高く設定することで人材を集めようとするブラック企業も存在するため、労働環境や待遇などについてもしっかりと調査したしょう。
仕事のやりがいは給料だけではありません。応募する企業は、さまざまな観点から比較検討して選ぶことが大切です。
大学時代の行動が就活の成否を分ける!
就活をするうえで「給与はあまり気にしない」という方も一定数いるでしょう。しかし、それは初任給には大きな差はない、という認識があるからではないでしょうか。
現在は、さまざまな企業が一律の初任給を廃止したり、平均額を大きく上回る初任給を支給していたりと、実力に応じた設定をする企業も少なくありません。
満足できる企業に入社するためにも、早め早めに就職活動をスタートすることが大切です。インターンシップやオープンキャンパスなども活用し「ここだ!」と自信を持って志望できる企業を探してみてください。
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
関連記事
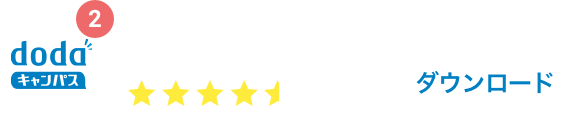



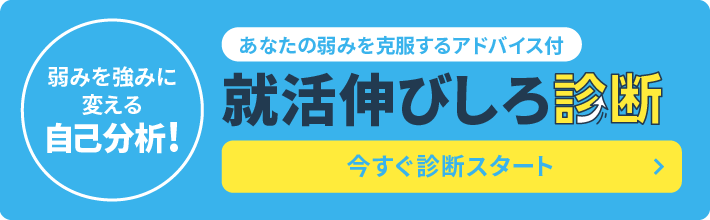
 シェア
シェア