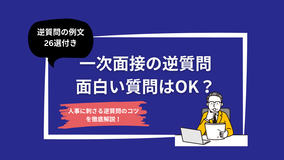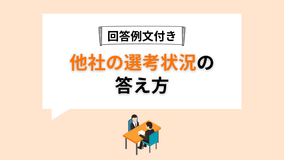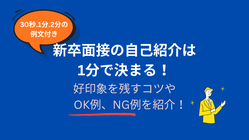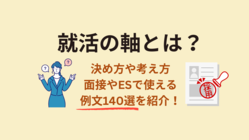面接で「苦手な人はいますか?」と聞かれることがあります。「そのまま正直に答えていいのかな…」「心が狭いと思われないかな…」と不安になる方もいるでしょう。
この質問は、答え方次第で相手の人格批判に聞こえやすく、評価を下げる恐れがあります。自分の価値観や対応力を前向きに示す答え方に整えましょう。
本記事では、「苦手な人」を聞かれた時の回答方法について具体的な例文を交えながら詳細に解説。面接の場で固まってしまわないよう、しっかりと独自の回答を準備しておきましょう。
目次
質問の意図は?企業が「苦手な人」を聞く理由
そもそも面接官はなぜ「苦手な人」を聞くのでしょうか?適切な回答を行うためには面接官の質問意図を理解し、それに沿った回答をすることが重要です。
本項では、面接官が「苦手な人」を質問する理由について解説します。
性格や価値観を知り、自社との相性を確認するため
面接官は、あなたの価値観が自社の風土・仕事の進め方と合うかを見ています。
たとえば、変化より手順の遵守が重視される職場で「現状維持を好む人は苦手」とだけ答えると、相性不一致と受け取られる恐れがあります。事前の企業研究で理念や働き方を把握し、自分の価値観と接点を見つけたうえで伝えましょう。
事前に企業研究を深め、企業の理念や社風を理解した上で自分の価値観と一致する点を見つけることが大切です。自分と企業がいかに相性が良いか「苦手な人」を通じてアピールしていきましょう。
苦手な人との接し方を知るため
職場では、考え方が異なる人と協力しなければならない場面も少なくありません。面接官は、そういった状況であなたが適切な対応ができるかを見極めようとしているのです。
対人関係のトラブルは、職場の生産性やチームワークに大きな影響を与えます。そのため「苦手な相手とも円滑にコミュニケーションを取ることができる」「苦手な人との接点から学び、成長に繋げることができる」といった人材は企業にとっても貴重です。
苦手な人とも協力し、組織の目標達成に向けて貢献できるという点が伝わるようにアピールしましょう。
面接官に好印象を与える回答のポイント
前述のとおり、面接官は「苦手な人」を聞くことであなたの価値観や苦手な人との接し方を知りたいと考えています。そのため、面接官に好印象を与えるためにはこの意図を踏まえて回答することが重要です。
納得感のある回答をするために、まずは自分自身の「苦手な人」に対する認識を明確にしましょう。そして、自己PRなど他の質問に対する回答と一貫性を保つことが大切です。
本項では、これらについて詳細に解説します。
「苦手な人」に対する自己理解を深める
面接で「苦手な人」を聞かれたときは、自分がなぜそのような人を苦手と感じるのか深く理解することが重要です。「苦手な人」に対する自己理解を深めることは、自分が大切にしている考え方や強みを見つけることに繋がります。
もしあなたが「時間にルーズな人」を苦手だと感じる場合、それは自分が時間を大切にしているからです。計画性やスケジュール管理を強みとして持っている可能性が高いでしょう。
自己理解を深める際は「なぜ」を5回自問自答することで真因やエピソードを見つけることができます。
自己理解を深める「なぜなぜ分析」の例
→なぜ苦手なの?
→自分の時間が無駄になってしまうから
→なぜ無駄になると困るの?
→他のスケジュールが崩れるから
→なぜスケジュールが崩れるの?
→細かくその日の実施事項を決めているから
→なぜ細かく決めているの?
→アルバイトで目前の業務に没頭したせいで完遂できなかった経験がある
➡アルバイト経験から時間管理への意識が高くなり、時間にルーズな人が苦手になった
自己PRなどの回答と一貫性を持つ
面接官が就活生の価値観や人柄を確認する質問は「苦手な人」だけではありません。自己PRや長所・短所、ガクチカと総合して判断します。
したがって、それぞれをバラバラに作らず、一貫した軸(例:論理性・協調・当事者意識など)で揃えましょう。
例)自己PRで「論理的思考」を示すなら、「感情に流されやすく議論が散漫になる場面が苦手」といった業務上の支障に紐づけると整合的です。
dodaキャンパスの就活軸診断では【所要時間5分】であなたが大切にしている価値観を言語化!診断結果はそのままキャリアノートに反映することができるので、あなたの大切にしたい軸に合った企業からオファーが届きやすくなります。

4ステップ!「苦手な人」の伝え方

「苦手な人」を聞かれた際は、わかりやすく、そして納得感のある回答をすることが大切です。具体的には、下記の4ステップで伝えることで面接官に好印象を与えることができるでしょう。
「苦手な人」を伝える際の4ステップ
- 「結論」を簡潔に伝える
- 苦手な「理由」を伝える
- 具体的な「エピソード」を伝える
- 苦手な人への対処方法と入社後の生かし方を伝える
各ステップについて詳しく解説します。
1)「結論」を簡潔に伝える
最初に自分が苦手と感じる人の特徴を一言で明確に伝えることが大切です。結論を簡潔に述べることで、面接官はその後の話を理解しやすくなります。
「協調性のない人が苦手です」や「時間にルーズな人が苦手です」のように、自分が苦手とする人の特徴をシンプルに表現しましょう。
なお、苦手な人の特徴を伝える際には、マイナスな表現はおすすめしません。「怠け者が嫌いです」といった攻撃的な表現は避け、「自主性のない人が苦手です」といった柔らかい表現に変換することを心がけましょう。
2)苦手な「理由」を伝える
結論を述べた後は、その人が苦手な理由を説明します。これにより、あなたの価値観や考え方、そして仕事に対する姿勢を深く理解してもらうことができます。
理由を伝える際は「協調性のない人が苦手です。なぜなら、チームで働く際に意見の共有や協力ができないと、目標達成が難しくなるからです」のように具体的に述べましょう。
ここでのポイントは、理由の中に自分が大切にしている価値観や信念を織り交ぜることです。面接官はあなたが組織の中でどのように活躍できるかをイメージすることができるでしょう。
3)具体的な「エピソード」を伝える
次に、理由を裏付ける具体的なエピソードを伝えてください。具体的な事例を挙げることで苦手な理由に説得力が増し、印象に残りやすくなります。
具体的なエピソードを伝える際のポイントは以下のとおりです。
エピソードを伝える際のポイント
- 状況を簡潔に説明する
いつ、どこで、誰と、どのような状況だったかを明確にします。 - 自分の感じたことを伝える
その時に自分が何を感じ、何を考えたのかを述べます。 - 客観的な視点を持つ
相手を批判するのではなく、事実をもとに話します。
4)苦手な人との接し方や入社後の生かし方を伝える
最後に、苦手な人に対してどのように接しているかをはじめ、どのように対処しているか、その経験を入社後にどう生かすかを伝えます。これにより、問題解決能力や成長意欲をアピールが可能です。
対処方法を伝える際は、問題解決に向けた前向きな行動を強調し、共存・協働の姿勢を示しましょう。
入社後の生かし方は、求める人物像や社風に結びつけ、具体的な貢献行動(例:定例の情報共有設計、傾聴・合意形成の進行役 など)まで言及できると効果的です。
あなたが大切にしている価値観を言語化できていますか?dodaキャンパスの就活軸診断はサクッと5分で企業選びの軸を診断!結果はそのままキャリアノートに反映することができるので、あなたの大切にしたい軸に合った企業からオファーが届きやすくなります。

「苦手な人」の回答例16選
ここでは「苦手な人」に対する回答例を16個紹介します。この中にあなたが苦手なタイプがあればぜひ参考にしてください。
また、自分に当てはまるものがあれば、それは短所の可能性があります。改善できないか検討すると良いでしょう。
挨拶ができない人
回答例
私は、挨拶ができない人が苦手です。挨拶はコミュニケーションの基本であり、良好な人間関係を築くために重要だと考えています。
私は大学で模型サークルに所属していますが、このサークルには誰にも挨拶せず無言で活動しているメンバーがいました。模型はチームで協力して大きな物を作成することもあります。しかしこのメンバーと他のメンバーとの間に距離が生まれ、チームワークに影響が出ていました。
私はその状況を改善するため、自ら積極的に挨拶をし、話しかけるように努めました。次第にそのメンバーも心を開き、挨拶を返してくれるようになりました。チーム全体の雰囲気も良くなり、大型模型の制作も順調に進むようになりました。
この経験から、改めてコミュニケーションの大切さを学びました。入社後も、自分から積極的に挨拶や声かけを行い、良好な人間関係を築いていきたいと考えています。
協調性が無い人
回答例
私は、協調性がない人が苦手です。チームで目標を達成するためには、メンバー同士の協力が不可欠だと考えているためです。
ゼミの方針を決める打合せで、一人のメンバーが自分の意見だけを主張し、周囲の意見を全く聞かない場面がありました。その結果、議論が進まず、活動の進行が遅れてしまいました。
私はそのメンバーに個別に話を聞き、彼の意見を尊重しつつ、他のメンバーとの調和を図る折衷案を提案しました。そして、その案を打合せで提示することで仲違いすることなくチームの快諾を得ることができました。また、当初協調性がなかったメンバーも周囲の意見を取り入れる大切さに気が付き、団結力が深まりました。
この経験から、協調性の重要性と多様な意見を取り入れる大切さを学びました。入社後も、チームワークを重視し、目標達成に向けて皆で協力したいと考えています。
常に批判的な人
回答例
私は、常に批判的な人が苦手です。前向きな姿勢で取り組むことが、良い結果を生むと考えているからです。
飲食店のアルバイト先で、新しいメニューを提案をすると必ず否定的な意見を述べる同僚がいました。そのため、周囲も提案を出しづらくなり、職場の活気が失われていきました。
私はその状況を改善するため、まず彼の意見に耳を傾け、なぜそう思うのかを理解しようと努めました。その上で、自分の提案のメリットを具体的に示し、建設的な議論を促しました。結果的に彼も協力的になり、職場全体の雰囲気が良くなりました。
この経験から、相手の意見を尊重しつつ、前向きなコミュニケーションを取る大切さを学びました。入社後も、積極的に意見交換を行い、チームの発展に貢献したいと考えています。
高圧的な人
回答例
私は、高圧的な人が苦手です。お互いを尊重し、意見を交換することが大切だと考えています。
大学のディスカッション演習で、リーダーが一方的に指示を出し、他のメンバーの意見を聞かない状況がありました。意見を出しても取り入れられないためメンバーのモチベーションが下がり、成果にも影響が出ました。
私はリーダーと直接話し、全員の意見を取り入れる重要性を伝えました。また、ミーティングの際には、各メンバーが発言できる機会を設けるよう提案しました。最初は受け入れてもらえませんでしたが、協力的に活動する他グループの成果を示すことで納得してもらうことができました。それ以降、全員が納得できる建設的な議論ができるようになり、最後のプレゼンまで成功させることができました。
この経験から、リーダーシップにおけるコミュニケーションの重要性を学びました。入社後も、相手を尊重しながら意見を伝え、良好な人間関係を築いていきたいと考えています。
時間にルーズな人
回答例
私は、時間にルーズな人が苦手です。時間を守ることは、他者への配慮であり、信頼関係を築くために重要だと考えています。
飲食店のアルバイトで、頻繁に遅刻してくるメンバーがいました。その結果、少人数で店を営業しなければならないことが多々あり、時には営業開始時間が後ろ倒しになってしまうこともありました。
私はそのメンバーと直接話す機会を設け、時間を守らないことで起きている弊害を伝えました。また、リマインドの連絡を入れるなど、フォローも行いました。結果、自分の遅刻による影響を自覚し、彼も時間を意識するようになりました。
この経験から、時間管理の重要性とコミュニケーションの大切さを学びました。入社後も、時間を守りつつ、周囲と協力して業務を進めていきたいと考えています。
責任感が無い人
回答例
私は、責任感がない人が苦手です。自分の役割を果たすことは、チームの成功につながると考えているためです。
ゴミ拾いのボランティア活動で、担当の地区を最後までやり遂げないメンバーがいました。そのため、隣の地区のメンバーが毎回その分をカバーしなければならず、負担が増えてしまっていました。
私はその状況を改善するため、なぜ最後まで完了できないのか直接ヒアリングを行いました。結果、ボランティアを行っている曜日に別の用件があり、途中で帰らなくてはいけないことがわかりました。そこで、彼の担当区域を減らし、他のメンバー全員で少しずつフォローできる体制を整えました。結果、彼は自分の担当分を責任を持って最後まで完遂できるようになりました。また、隣の地区を担当しているメンバーの不満も解消され、活動が円滑になりました。
この経験から、責任感の大切さとチームワークの重要性を学びました。入社後も、自分の役割をしっかりと果たし、チームに貢献したいと考えています。
言い訳が多い人
回答例
私は、言い訳が多い人が苦手です。問題に直面したときは言い訳ではなく、解決策を考えることが大切だと考えています。
私の研究室では微生物の増殖環境を特定する研究を行っています。この研究室に研究が進まない理由を研究の難易度や他人のせいにする先輩がいました。研究テーマはそれぞれに関連性があり、一人が遅れると全員の進捗に影響が出てしまうという特徴がありました。
私は、彼と一緒に研究が進まない根本的な原因を洗い出し、解決策を考えました。複数の論文を読み、彼の研究を進めるためには微生物の初期数を増加させる必要があることを見出しました。結果、当初の仮説通りに微生物を増殖させることに成功し、他のメンバーの研究も進めることができました。
この経験から、責任を持って行動することと、建設的に問題解決をする大切さを学びました。入社後も、課題に対して前向きに取り組み、成果を上げたいと考えています。
嘘をつく人
回答例
私は、嘘をつく人が苦手です。事実が共有されず、不正確な情報が流通すると考えるからです。信頼関係は誠実なコミュニケーションから生まれると考えています。
コンビニのアルバイト先で、ミスをしたときに嘘をついてごまかす同僚がいました。ある日彼が1日の会計を集計していたところ、10円足りないという事件が発生。しかし彼は問題をもみ消すため、自分の財布から10円補填することを選びました。結果、無いと思われた10円が後から見つかり、なぜ10円多いのかという別の問題になってしまいました。
私は彼に正直に報告することの重要性を伝えました。また、ミスを共有し、皆で解決策を考えるよう提案しました。その結果、彼も誠実に対応するようになり、職場の信頼関係が深まりました。
この経験から、不利な情報も速やかに共有することの重要性を学びました。
感情的になりやすい人
回答例
私は、感情的になりやすい人が苦手です。冷静な判断が、良い結果を生むと考えているからです。
私が入っているテニスサークルには、意見が対立すると感情的に怒り出すメンバーがいました。そのため、練習メニューの決定に時間がかかり、活動開始が遅れてしまうことが多々ありました。また、彼が怒ることを知っている他のメンバーは萎縮し、怯えながら活動することも少なくありませんでした。
私はその状況を改善するため、冷静に意見交換ができる環境を作るよう努めました。話し合いのルールを設定し、一人一人が順番に発言する場を設けました。その結果、感情的な衝突が減り、建設的な議論ができるようになりました。
この経験から、冷静なコミュニケーションの重要性を学びました。入社後も、感情に流されず、客観的に物事を判断できるよう心がけたいと考えています。
陰口が多い人
回答例
私は、陰口が多い人が苦手です。直接話し合うことで、誤解を解消し、良好な関係を築くことができると考えています。
私が所属しているサッカー部の先輩に、陰で他のメンバーの悪口を言う人がいました。結果、メンバーは疑心暗鬼となり、チームワークを発揮することができませんでした。
チーム競技で協力できないことは大きな問題であると考え、チーム内で活発なコミュニケーションを促しました。定期的なミーティングを行い、意見や不満を直接話し合える場を作りました。その結果、誤解が解消され、チームワークが向上しました。
この経験から、オープンなコミュニケーションの重要性を学びました。入社後も、多様な人と誠実に対話し、信頼関係を築いていきたいと考えています。
優柔不断な人
回答例
私は優柔不断な人が苦手です。迅速な意思決定が、仕事の効率を高めると考えています。
私の所属する旅行サークルでは毎月メンバーが持ち回りで旅先を決めるというしきたりがあります。しかしメンバーの一人がなかなか行き先を決断できず、航空券のチケットや宿が埋まってしまったことがありました。結果、その月の旅行は中止となりました。
私は同じことが繰り返されないよう、旅行先の候補を一覧にまとめ、メリット・デメリットを明確にしました。また、持ち回りのメンバーが迷って動けなくならないよう、月に1回ミーティングを開き、進捗状況を共有する場としました。その結果、翌月以降はスムーズに意思決定が行われ、毎月の旅行を楽しむことができています。
この経験から、意思決定の重要性とサポートの大切さを学びました。入社後も、積極的に業務改善の提案を行い、チームの成果に貢献したいと考えています。
マナーに欠ける人
回答例
私は、マナーに欠ける人が苦手です。必要最小限のマナーは、お互いが気持ちよく活動するために必要だと考えています。
私が務める飲食店のアルバイト先で、お客様に対して失礼な態度を取る同僚がいました。結果、クレームの件数は増加し、店の評判にも影響が出てしまいました。
私はその状況を改善するため、彼にマナーの重要性を伝え、一緒に接客マニュアルを見直しました。また、ロールプレイングを行い、適切な対応を身につけるサポートをしました。その結果、彼の接客態度が改善し、お客様からの評価も上がりました。
この経験から、マナーの重要性と指導の大切さを学びました。入社後も、基本を大切にし、周囲と良好な関係を築きたいと考えています。
人の話を聞かない人
回答例
私は、人の話を聞かない人が苦手です。相手の意見を尊重することが、良いコミュニケーションの基本だと考えています。
大学2年生の時、クラスのディスカッションで自分の主張だけを繰り返し、他人の話を遮るメンバーが2名いました。彼らの意見は完全に対立し、お互いの意見を無視し続けたことで議論は硬直。結果、結論に至りませんでした。
私はその状況を改善するため、話し合いのルールを提案し、一人ずつ発言する場を設けました。また、相手の意見を要約して確認する「アクティブリスニング」を取り入れました。その結果、メンバー全員が意見を共有でき、議論が深まりました。
この経験から、相手の話を聞くことの重要性を学びました。入社後も、傾聴の姿勢を大切にし、円滑なコミュニケーションを図りたいと考えています。
連絡が無い人やレスポンスが遅い人
回答例
私は、連絡がない人やレスポンスが遅い人が苦手です。迅速な情報共有が、業務の効率化につながると考えています。
学園祭の実行委員長をした際、委員の中に連絡が遅く進捗状況の共有がないメンバーが数名いました。彼らが担当する予算の使用状況も把握できず、他のタスク管理やスケジュール調整が難しくなりました。
私は状況改善を目的に、委員全員が参加するグループチャットを開設し、その中で定期的な報告の時間を設けました。これにより、周囲の報告に感化され彼らも報告してくれるようになりました。また、進捗を共有できるツールを導入し、チャット内で常に確認できるプラットフォームを作成することで状況を見える化しました。
この経験から、迅速な連絡と情報共有の重要性を学びました。入社後も、こまめな報告・連絡・相談を心がけ、業務を円滑に進めたいと考えています。
気分によって言うことが変わる人
回答例
私は、気分によって言うことが変わる人が苦手です。一貫性のある対応が、信頼関係を築くために重要だと考えています。
本屋でアルバイトをしていた際、店長の指示内容がその日によって変わっていました。スタッフも、どの行動を行うことが正しいかわからず、常に一歩遅れた対応を行うしかない状況でした。
私はその状況を改善するため、店長に業務フローの明確化を提案しました。また、店長にヒアリングをしながら標準作業のマニュアルを作成し、全員が同じ基準で働けるようにしました。このように正しい作業を明確化した結果、指示のブレがなくなり、業務効率が向上しました。
この経験から、一貫性のあるコミュニケーションの重要性を学びました。入社後も、的確かつ整合性のとれた情報共有を心がけ、信頼される社会人になりたいと考えています。
無神経な発言をする人
回答例
私は、無神経な発言をする人が苦手です。相手の気持ちを考えて行動することが円滑なコミュニケーションをする上で大切だと考えています。
インターンシップに参加した際、他人の意見を攻撃的な表現で否定し、相手を傷つける発言をするメンバーがいました。その結果、チームの雰囲気が悪くなり、ディスカッションは盛り上がらず業務の進捗にも影響が出ました。
私はプライベートでそのメンバーと直接話をする場を設け、発言の影響について伝えました。また、毎回議論の内容をボイスレコーダーに取り、後で全員で聞き返して相手を傷つける発言がないかチェックする仕組みを作りました。その結果、彼だけでなく全員が自分の言動に気をつけるようになり、チームの雰囲気が良くなりました。
この経験から、思いやりの重要性とコミュニケーションが成果に及ぼす影響力を学びました。入社後も、相手を尊重し、良好な人間関係を築きたいと考えています。
dodaキャンパスの就活軸診断では【所要時間5分】であなたが大切にしている価値観を言語化!診断結果はそのままキャリアノートに反映することができるので、あなたの大切にしたい軸に合った企業からオファーが届きやすくなります。
「苦手な人」を聞かれたときのNG内容と回答例
「苦手な人」は自己PRやガクチカと異なりマイナスを尋ねる質問であるため、面接官に悪印象を与える回答も存在します。
面接の場で間違えてしまわないようにNGとなる内容を確認しておきましょう。具体的なNG回答例も紹介するのでぜひ覚えておいてください。
「苦手な人はいません」と答える
「苦手な人はいません」という回答は一見ポジティブに聞こえますが、「自己分析が足りていない」「人間関係に無頓着」と解釈される可能性があります。
どんな人にも合わないタイプが存在することを理解し、そのような時にどう対処するかに焦点を当てて回答しましょう。これにより、柔軟な対応力や協調性をアピールすることができます。
NG回答例
私には苦手な人はいません。コミュニケーション能力が強みであるため誰とでもすぐに打ち解けることができるからです。
御社に入社後もこの強みを生かし、さまざまな人と協力して業務を全うしたいと考えています。
「苦手な人とはかかわりません」と答える
この回答は、協調性や柔軟性が欠けていると判断される可能性があります。職場では、さまざまな人と協力して業務を進める必要があるため、苦手な人を避ける姿勢は良い印象を与えません。
ビジネスでは、マッチしない性格でも適切に対処できる能力は重要です。苦手な人を避けるのではなく、どう向き合うかを示しましょう。
例えば下記の回答では、問題を回避する姿勢が強調されてしまい、チームワークや問題解決能力に不安を抱かせます。
NG回答例
私は苦手な人とはかかわらないようにしています。自分が苦手であるということは相手も苦手に感じている可能性が高いためです。かかわりを避けることでお互いのためになると考えています。
御社に入社後も相手のことを考え、お互いが高パフォーマンスを発揮できる人間関係を築いていきたいと考えています。
ネガティブな回答をする
「〇〇な人が嫌いです」や「〇〇する人とは関わりたくありません」といった回答は、否定的な印象を与えるだけでなく、コミュニケーション能力や協調性が不足していると捉えられる可能性があります。
他人の欠点を強調するのではなく、自分がどう対処するかに焦点を当てると良いでしょう。建設的な姿勢を示すことで、面接官に好印象を与えることができます。
NG回答例
怠け者で無責任な人が苦手です。自分の業務を全うしない人のせいで周囲の負担が増えて迷惑します。
私の所属するアルバイトにも、自分の分担業務を完遂せず、定時で帰宅していく先輩がいます。彼のせいで私を含めた同僚は常に負担が増え、残業となることも少なくありません。
私は彼を反面教師とし、御社に入社後も自分の仕事に責任感を持って最後までやり切りたいです。
苦手な人を一方的に否定する
「〇〇な人には耐えられません」などと一方的に否定する回答は、他者への配慮や理解する姿勢が不足していると受け取られる可能性があります。
一方的な否定ではなく、なぜ苦手と感じるのか、その理由を客観的に説明し、自分がどう対応するかを示すことが大切です。例えば、下記の回答をすると強い否定的な表現が含まれており、協調性に欠ける印象を与えてしまいます。
NG回答例
自分勝手で他人のことを考えない人です。
私は親から「人を思いやることの大切さ」を学んできました。そのため、自己中心的な考えをする人を理解することができません。
御社に入社してからも常に相手のことを考えて接し、多様な人と良好な関係を築いていきたいと思います。
「苦手な人」を聞かれたときも自分のアピールに繋がる回答をしよう
面接で「苦手な人」に関する質問は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、自分の価値観や強みをアピールする絶好の機会でもあります。
大切なのは、単に苦手なタイプを伝えるのではなく、苦手な人との接し方や接点を通じて学んだ内容を具体的に示すことです。さらに、その経験が今後の職場でもどのように役立つかを伝えることで、面接官に対して自分の適応力や問題解決能力をアピールすることができます。
丁寧に自己分析を行い、ポジティブな視点で対応しましょう。
▼ストレス耐性やリーダーシップ…など、 自分では気づかなかったパーソナリティや強みを知りたい方はこちら
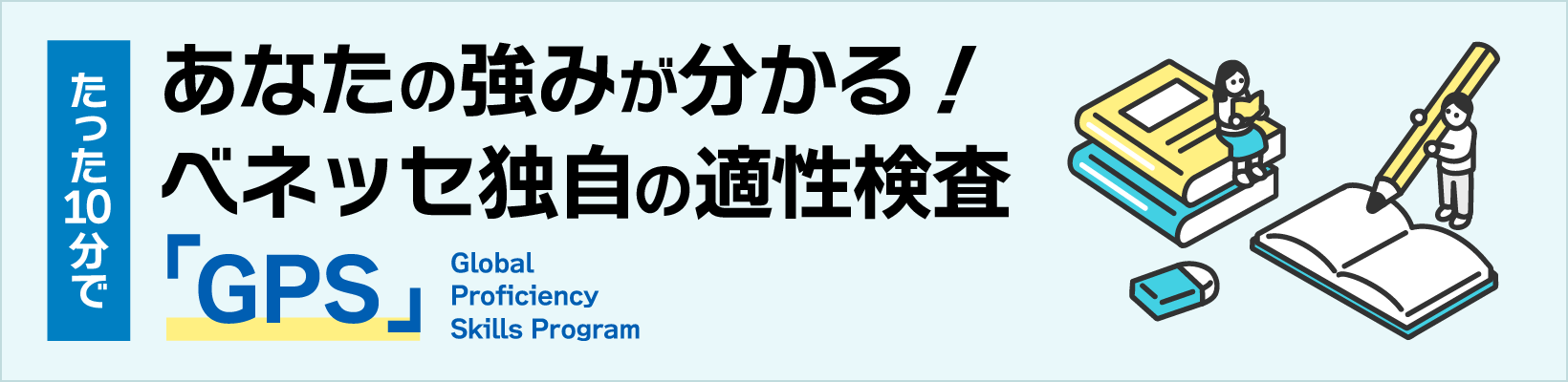
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
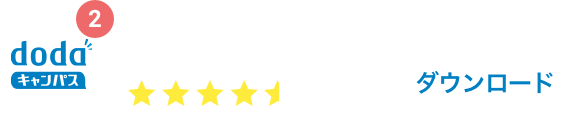



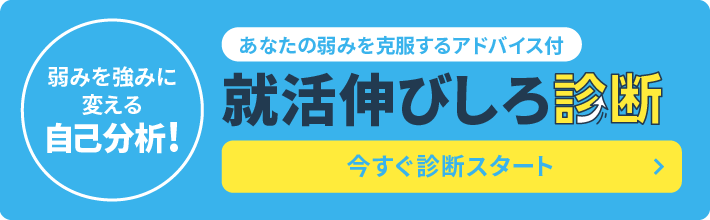
 シェア
シェア