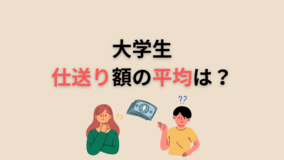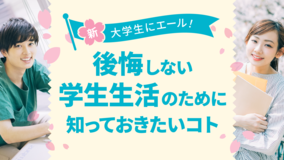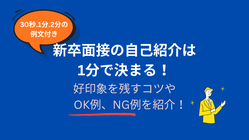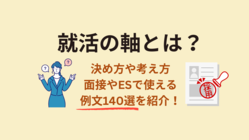2022年以降続く物価高騰は、私たちの生活にじわじわと大きな影響を与えています。「この値上げ、いつまで続くの?」「給付金って本当にまたもらえるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、なぜ今の物価高が起きているのか、そして注目されている3万円給付金の最新情報(2025年版)、今後の物価動向や生活を守る具体的な対策までをわかりやすく解説します。
将来に備えるヒントもあわせて紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
いま起きている「物価高騰」の背景とは?
急激な値上げが続く今、「一体なにが原因なの?」「いつまで続くの?」という疑問を抱いている方も多いかもしれません。ここでは、物価高騰が起きている主な背景をわかりやすく解説します。
CPI(消費者物価指数)から見る物価上昇率
日本の物価は、2021年の後半から物価が上がりはじめ、インフレ傾向が続いています。
2024年時点でもCPI(消費者物価指数)は上昇基調であり、特に、日用品や食料品の値上げが家計を直撃。生活者の負担が増しています。
なぜここまで物価が上がっているの?
物価高騰の背景には、特に下記3つのような影響が複合的に重なっています。
- 原材料価格の高騰と供給制約
👉エネルギーや穀物などの原材料価格が上がり、ウクライナ情勢などの影響で供給も不安定に。これが物価高騰の一因となっています。
- 円安の影響(日本と米国の金融政策の違い)
👉日米の金利差で円安が進行。輸入品の価格が上がり、食料やガソリンなど多くの品目で値上げが起こる原因となっています。
- 人手不足や物流コストの増大
👉人手不足により人件費が上がり、燃料高騰で物流コストも増加。その分が商品の価格に反映され、家計に影響しています。
これらの要因が重なり、生活必需品の価格上昇によって体感的なインフレが深刻化しています。

📌 将来への不安、少しでも減らしたいあなたへ
物価高騰が続く中、今から“自分に合う働き方”を見つけておくことが大切です。 dodaキャンパスなら、大学1・2年生から始められるキャリア講座や企業オファーが充実! 働き方・業界研究に役立つ情報も無料で受け取れます。
\無料はもちろん登録!/
物価高騰が家計に与える影響
最近は食べ物や日用品の値段がどんどん上がっていますが、仕送りやアルバイト代ではカバーしきれない出費が増え、やりくりが難しいと感じる学生も増えています。 結果、手元に自由に使えるお金が少なくなる状況が起きています。
特に、生活に必要なものに多くのお金を使わないといけない人ほど、物価高の影響を強く感じやすく、家計がますます厳しくなる傾向にあります。
最新の「物価高騰対策給付金」はいつ?誰が対象?
物価の上昇にともない、生活が苦しくなったという声も多く聞かれます。そんな中、政府が実施する「給付金制度(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金*)」が注目を集めています。
ここでは、給付金の最新情報や対象者、受け取り時期などを解説します。
※電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を給付される給付金
参考元:内閣府「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関するよくあるご質問」
2025年版・給付金の概要(3万円支給)
政府は、2025年も「物価高騰対策臨時くらし応援事業」を継続する方針を示しています。
この施策は、物価上昇による家計の負担を軽減することを目的としたもので、主に住民税非課税世帯などの生活にゆとりが少ない家庭を対象に、 1世帯あたり3万円の給付金を支給する予定です。2024年に実施された同様の支援に続く措置であり、生活支援策として注目されています。
支給対象は?(非課税世帯、低所得世帯など)
<主な給付対象者>
- 住民税非課税世帯
- 住民税課税で所得の少ない子育て世帯や年金生活者
上記の通り、大学生自身は対象外になることもありますが、実家が住民税非課税世帯などの場合、給付金の対象になる可能性もあります。ご家族と確認してみましょう。
主な対象は住民税非課税世帯のほか、住民税が課税されていても所得の少ない子育て世帯や年金生活者など。ただし、対象の範囲や条件は自治体によって異なる場合があるため、最新の情報を確認することが大切です。
「給付金3万円」はいつもらえる?スケジュールは?
2025年の物価高騰対策給付金は、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円が支給される制度です。
さらに、18歳未満の子どもがいる世帯には子ども1人あたり2万円が加算されます。給付はすでに2025年5月までに多くの市区町村で開始済みで、申請不要で自動的に振り込まれるケースもありますが、自治体により手続きが異なるため注意が必要です。
あわせて、電気・ガス料金の負担を約3,000円引き下げる支援も2025年夏から秋(令和7〜9月)にかけて実施予定です。詳細な給付時期や手続き方法は、お住まいの自治体の公式ページで必ず確認しましょう。
自分や家族が対象になる可能性も!「非課税世帯向け給付金」の注意点と申請方法
給付金の支給は自治体によって対応が異なり、申請が必要なケースもあります。確実に受け取るためには、下記ポイントを押さえておきましょう。
- 自動給付ではないケースもあるため、申請が必要
- マイナンバーと住民票の情報連携により、案内が届く仕組みも
- 本人確認書類や口座情報の準備を忘れずに

💡生活の支援だけでなく、“将来の自立”も大切にしたいあなたへ
dodaキャンパスでは、就活期だけでなく、大学1・2年生のうちからキャリアを考えられる講座やイベントを多数用意しています。
物価や将来の不安に備え、自分に合った環境を見つけてみませんか?
\無料はもちろん登録!/
物価高騰はいつまで続く?専門家の見解と今後の見通し
「この物価高、いったいいつまで続くの?」という不安の声が多く聞かれます。ここでは、専門家の見解や政府の予測をもとに、今後の物価動向を読み解いていきます。
インフレ率の動向と2025年の予測
2025年も当面はインフレ率2〜3%台で推移する見通しです。原材料や人件費の高止まりにより、物価はすぐには下がらないと予想されています。
「物価高騰 いつまで」不安を抱える生活者の声
SNSやアンケートでも「この物価はいつまで…」という不安が多数。給付金で一時的にしのげても、生活設計の見直しを迫られる声が目立ちます。
生活を守るためにできる3つのこと(支援制度まとめ)
物価高騰が続く中で、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。ここでは、少しでも生活の負担を減らすために、今すぐできる3つの対策を紹介します。支援制度の活用や家計の見直しなど、将来に備えるヒントとしてお役立てください。
1. 地方自治体の支援制度を活用する
国の給付金以外にも、各自治体が独自に行っている支援制度があります。たとえば、食費の補助、光熱費の一部サポート、学校給食費の免除など、家庭の負担を軽減する取り組みが用意されています。
対象条件や申請方法は自治体によって異なるため、お住まいの地域の公式サイトを確認し、利用できる支援を積極的に活用しましょう。
2. 家計の見直し・節約術を取り入れる
物価が上がる今こそ、家計を見直すチャンスです。スマホの料金プランを見直す、食費や日用品の節約を工夫するなど、日常の工夫で出費を抑えることが可能です。
収入がすぐに増えなくても、無駄を減らすことで生活を安定させる手段になります。小さな見直しでも積み重ねが大切です。
3. 最新情報をチェックし、給付金を逃さない
給付金や支援制度の情報は、自治体によって告知方法や申請期限が異なるため、こまめなチェックが欠かせません。「〇〇市 物価高騰 給付金 最新」といった具合に、定期的に検索してみましょう。
また、市区町村のLINE公式アカウントや広報誌をフォローするのもおすすめです。知らずに損をしないよう、情報収集も生活防衛のひとつといえます。

📌 将来への不安、少しでも減らしたいあなたへ
物価高騰が続く中、今から“自分に合う働き方”を見つけておくことが大切です。 dodaキャンパスなら、大学1・2年生から始められるキャリア講座や企業オファーが充実! 働き方・業界研究に役立つ情報も無料で受け取れます。
\無料はもちろん登録!/
無料
- ▼ 自己分析に役立つ適性検査(GPS)
- ▼ 自己PR添削
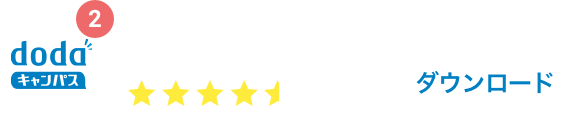

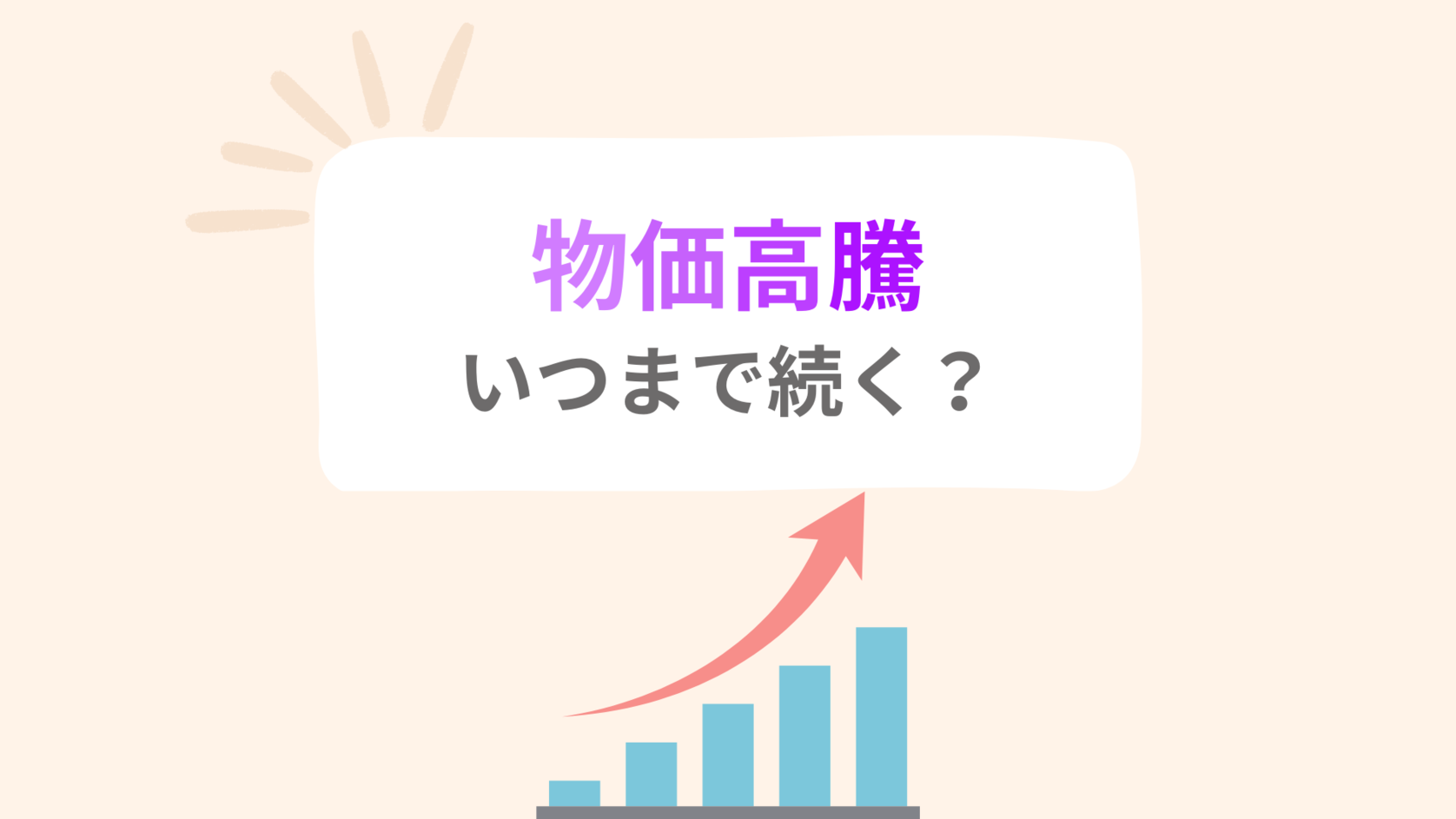

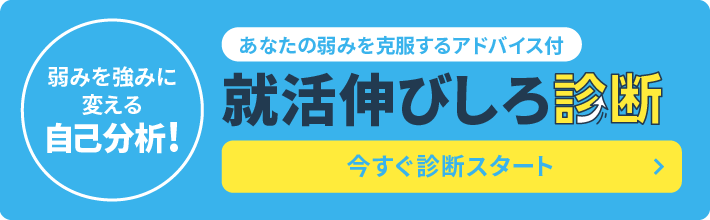
 シェア
シェア