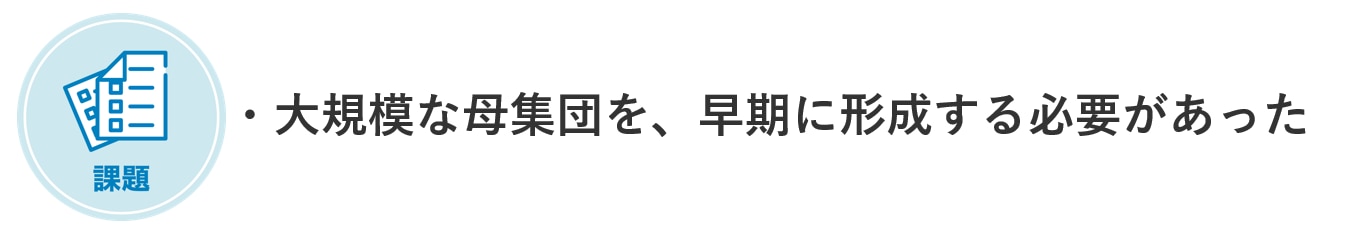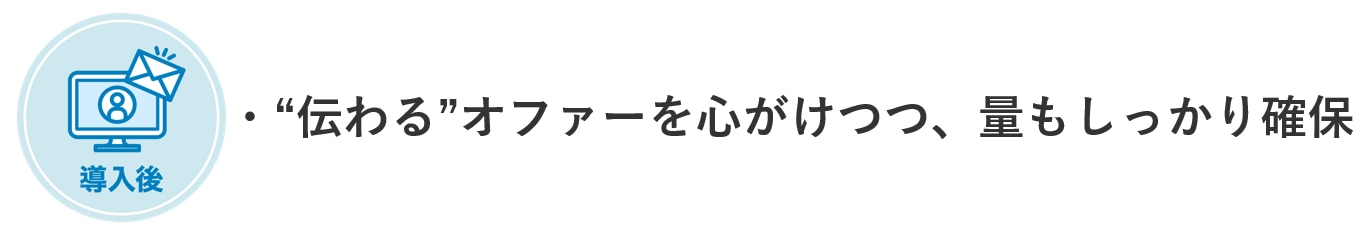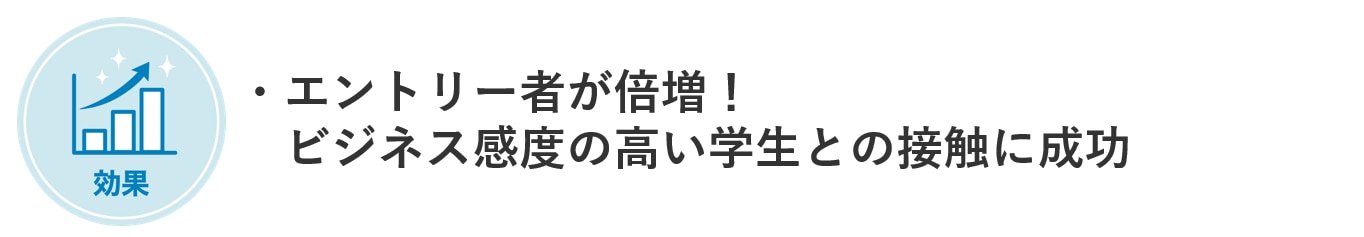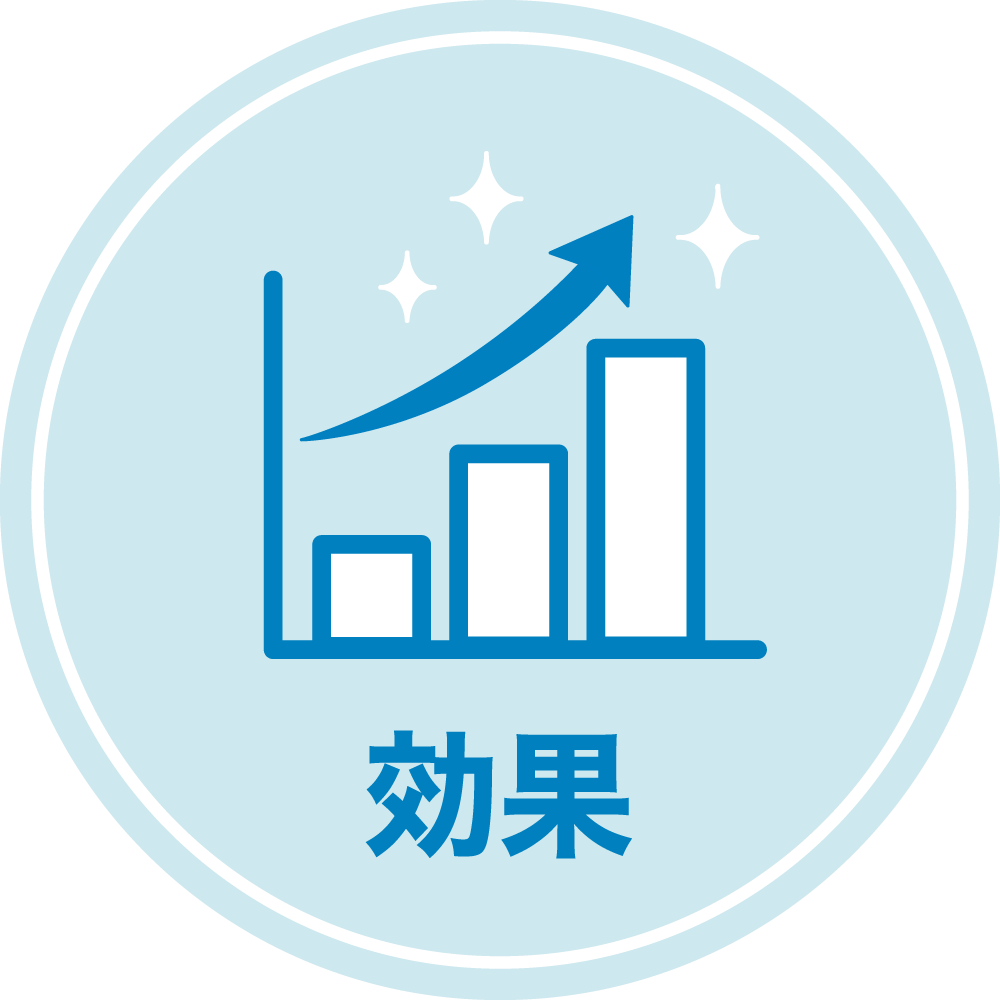大規模な母集団を、早期に形成する必要があった
①採用活動の方針
蒲原様:課題は早期の母集団形成です。当社は例年500名前後を採用目標数に掲げており、もともと母集団形成は課題でした。加えて近年は採用活動の早期化が著しく、採用スケジュールを前倒ししないと、4年生10月の内定式までに採用活動を終えられない可能性がございます。こうした状況から、少しでも動き出しを早めて、早期に母集団を形成する必要があると感じていました。
蒲原様:全体で8つの媒体を導入しており、うち3つがダイレクトリクルーティングです。ナビサイトもダイレクトリクルーティングも、1つのツールだけでは採用し切れる目標人数ではありませんので、複数のツールを並行して活用しています。
蒲原様:母集団形成を行う時期の違いは大きいですね。ナビサイトはシステム上、学生さんがエントリー可能になる時期が決まっていますが、ダイレクトリクルーティングはスタート時期を企業側で決めることができます。特にdodaキャンパスは低学年から登録している学生さんも多く、早いタイミングでオファーを送付できます。先にお伝えしたように、母集団形成においてはナビサイトも欠かせないのですが、動き出しを早めるという点では、ダイレクトリクルーティングに大きな期待を抱いています。
蒲原様:1つ目に、オファー送付の手順がシンプルであることが挙げられます。オファーを送るうえで必要な設定が少なく、工数がかからない分、オファーの数を確保しやすいですね。2つ目は、一度オファーを断れても、一定期間を空ければ同じ学生さんに再オファー可能なこと。採用活動も後期になると、ターゲットとなる学生さんは減っていきます。そうした際でも打ち手がなくならないのは、大きなメリットだと感じています。
また、「オファーリクエスト」も特徴的ですね。オファーリクエストがあるからか、dodaキャンパスは他のダイレクトリクルーティングと比較しても、オファー承諾率が高いです。
※オファーリクエストとは
企業が「検討中」に追加したことを学生に通知して、企業に興味を持った学生から、オファー送信のリクエストを受け取れる機能です。オファー送信前に自社に興味ある学生が分かるため、承認率の向上に繋げることができます。